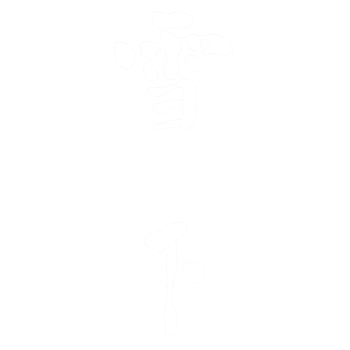四月は宗教行事の多い月である。
まず第一日曜日に、集会所で念仏講というのがあった。家にお知らせの紙が配られていたので知ったのだが、なんなのか母に訊いてみたら、このあたりの婦人たちが集まってなにかする会だが、参加したことがないのでよくはわからないという。
母の話を聞きながら、わたしは白いコピー用紙に印刷された「念仏講」の文字をもう一度眺めた。「講」である。それに念仏がくっつくのである。どうしても行かねばならないと思った。
「講」は日本の地域社会に根ざしたある種の集団、結社のことを指す。本来は寺院内で仏典を講じたり研究したりする坊さんたちの集会を意味していたが、それがしだいに世俗社会でも用いられるようになって、なにごとか結社のような性質をもつ閉じた集まりを「講」と称するようになったようである。ものの本によると、平安時代、貴族階級に仏教信仰が広まると、貴族たちは贅を尽くして種々の仏教儀礼を主催するようになるが、当時は法華信仰が流行していたこともあって、法華八講というのが特に盛んに行われた。これは坊さんが法華経を一巻ずつ読み、その講釈をするのを聞く集会のようなもので、「講」という言葉はこのあたりから民間へ広まっていったものらしい。
講の概念はしだいに各地の土着信仰や産土神信仰、自然信仰などへも浸透してゆき、そうした信仰に基づいて宗教行事を担う集団の多くが講の名で呼ばれるようになった。山の神講や田の神講、ある特定の日に眠らずにこもり明かして、月の出、日の出を拝する月待講や日待講のようなものもある。日本各地でこれらの風習がどれほど残っているものかは知らないが、わたしの住む地域ではどうやら現役で生き残っており、念仏講はそうした古くからの宗教行事を行う集まりのひとつに違いなかった。
母曰く、それはわたしの祖母世代の人たちがこれまで担ってきた地域行事のひとつであろうという。だがおおむね九十を超える女性たちであるから、特にここ数年、コロナ騒ぎも相まって行事の継続が困難になっていた。このままでは地域行事が途絶えてしまうというので、先だってこの祖母世代の人たちよりひと世代若い人たち、つまりわたしの母親世代の人たちが集まって、どうするか話し合いをしたそうである。
母もその集まりに誘われたが、参加しなかった。話し合いとは半分口実で、ただ集まっておしゃべりするだけだというのである。そういえば祖母も婦人たちの集まりには一切顔を出さなかった。地域婦人たちは、あれこれの伝統行事を行うほかにも、ときどき集会所に集まって茶飲み話などしていたものであるが、祖母はこの手の集まりを嫌っていた。あんなものに顔を出すくらいなら、家の仕事をしていたほうがよほどましだというのである。
血統からいえば、わたしは当然この気高き精神を受けついで、念仏講などに顔を出すような人間にはならないはずである。ところがわたしは根が卑しいのであろう、家風を守って孤高を持するには好奇心が強すぎた。それで、我が家の長きにわたる慣習を恥知らずにも捨て去って、のこのこ出かけることにしたのである。
時代が下るごとに、品性は劣化する。昔の人はよく云ったものである。
日曜日は晴れていた。四月とはいえ、田んぼや道ばたにはまだ多く雪が残っていた。わたしはそうしたものをわざと踏んだりして歩いたが、日差しは暖かく力強く、まぎれもなく春のものであった。この地方では、こうした春先のごく限られた日にだけ、地中海のものを思わせる乾いた明るい日差しが、空を青々と染め、ものの影を明瞭に、くっきりと浮かび上がらせる。わたしは道を歩きながら、いま自分はギリシアにいるのだと想像する。ギリシアの小さな、壁一面聖書の場面を描いた壁画に満たされた古い教会に、いま歩いて向かっているのだと。
子どものころ、このような空想のもと家の周りを歩きながら、わたしは世界じゅうを旅した。どのような国の風土でも、家の周りに見出せないものはなく、わたしは必ずどこかから、テレビや写真で見たパリの並木道に、アルプスの山々に、中国の切り立った岩山に似たものを見つけてきて、自分がそこにいるように思いこんだものである。
家を出てしばらく行くと、ややくねったようなゆるやかな十字を描く辻に出る。その辻角に、三体のお地蔵様をまつった小さなお堂がある。お堂の横には名前のわからない大きな木があり、子どものころ、夏の盛りに遊び疲れたりなどすると、わたしたちはよくその木陰でひと休みした。ちらちらと揺れる木漏れ日のなかで休憩していると、近くの用水路を勢いよく流れる水の音が聞こえてきて、なんだか涼しげな気分になり、一同やがて元気をとり戻してまた遊びに出かけた。
わたしたちが休んでいると、ときどきお地蔵様の向かいにある小さな商店から、店番をしているお婆さんが出てきて、わたしたちにあめ玉やガムなどをくれた。お地蔵様におそなえされているお菓子を持っていってもよいと云ってくれることもあった。お地蔵様の前には、いつもお茶の入った茶碗が三つ置かれていて、そこに誰かが必ずおそなえものを置いていた。たいていは袋に入った菓子だったが、ときどきゆでたトウモロコシや赤飯などをそのまま置いてゆく人があって、そのせいでお堂の中は常時アリやハエのたまり場になっていたから、わたしたちはたいてい、いただくのを遠慮したのである。
集会所はこのお地蔵様のお堂の裏にあるのだが、その手前で、数人のご婦人たちが立ち話をしていた。はじめわたしが誰だかわからなかったようで、皆なにやら困惑したような顔をしていたが、わたしが名乗ると、今度はいっせいに驚いたような顔をして、「あれまあよう来たこと」というようなことを云う。
その中に、わたしの幼なじみの母親がいた。二軒隣の家に住んでいる幼なじみはわたしと同学年で、昔よく一緒に遊んだものであるが、この幼なじみはちょうどわたしのように、もう長いこと働きもせず、ただ家にいる。彼は元気かと訊ねると、母親は困ったような顔で、あの子はちっとも外に出ないので困っている、今度遊びに来いと云った。
ご婦人たちのあとについて集会所に入った。中は十五畳くらいある畳敷きの部屋になっている。十人近い女性たちがすでに集まっていて、皆ふり返ってわたしを見た。わたしが母の代理で来ましたと云って頭を下げると、若い人が来るのはいいことだ、というようなことを口々に云った。集まった人たちは、一番若い人でも五十代で、一番上は、わたしの伯母と同級生の、七十四になるご婦人である。日本舞踊をやっていて、小柄だがほれぼれするほど姿勢がよくスタイルもよく、服装や化粧もちょっと垢抜けている。
参加者がそろうのを待つあいだに、念仏講とはなんなのかあたりの人に訊ねてみたところ、このように教えてくれた。そこのお地蔵さんあるべえ、あのお地蔵さんさ念仏上げて、子どもの安全とかなんとか、とにかくいろいろ、お願いするのしゃ。
「そういえば、行事ってばなんでも、子どもさ関係したもの多いな」
と、幼なじみの母親がひとりごとのようにぽつんと云った。
ほどなくみんな集まって、念仏講がはじまった。必要な道具はすべて部屋の隅に置かれた古い木箱のなかに保管されており、持ち手のついた小さな丸い鉦とそれを叩く棒、それに巨大な数珠が箱からとり出された。何メートルもある紐に、手のひらくらいある円筒型の木の玉を通した数珠は、ずいぶん古いものらしく、玉が黒光りしている。何十年も使われたロザリオが、摩耗と人の手垢で光ってくるのと同じである。
道具の用意が終わると、ひとりの女性が立ち上がり、まずは念仏をはじめる前に、鉦叩きの係が鉦を叩いてあたりを回らねばならないといって、自らその役を引き受け、鉦をもって外に出て行った。その女性は集会所の鍵を管理している関係で、年寄りとのつきあいが多く、こういうことにかけては一番のもの知りなのだという。
カンカンという独特の甲高い音があたりに響き渡り、しだいに遠ざかる。昔はトラックの荷台に乗って回ったこともあったというようなことを、誰かが話した。昔は子どもも多く、人手も多かった、だからこんなこともやった、あんなこともできた、というような話が、しばらく続いた。
いまこの集落に、子どもは片手で数えるほどしかいない。当然結婚して子どもをもっているべき年齢の人間は、なぜかわたしや幼なじみのようにしくじれてしまって、仕事もしない結婚もしないで無為に時を過ごしている。いま集会所に集っているこの世代の人たちが高齢になったら、もう地域行事の担い手などいなくなってしまうかもしれない。もう少し若い世代になると、そんなものに興味もなく、集まってなにかやろうなどと云いだすほど、互いのことを知らないし、つきあいもないからだ。
鉦叩きが戻ってきて、念仏講の詳しいやり方を説明しはじめる。まず参加者は、鉦叩きを中心に輪になって座り、長い数珠を手にとる。そして数珠を隣の人に送って回しながら、念仏を唱えるのだという。数珠には大きな丸い玉がひとつついているが、それが自分の手元に回ってきたら、頭を下げて拝む。穴のあいた古銭を紐でくくったものがあって、数珠が一周するたびに左に寄せた銭をひとつずつ右へずらしてゆき、全部右側へ移るまで念仏を続ける。
十一名の参加者は、だいたいわかったという顔でうなずき、なんとなく部屋の真ん中に輪になって座った。めいめいに数珠を取りあげて、さあはじめようとなるが、ところで念仏はどういうものか、数珠はどっち回りに回すのか、誰もよくわからない。誰それに訊けばわかるのにとか、昔参加したのにとかいう嘆きが聞かれる。唱えるのは南無阿弥陀仏ではなかったかと誰かが云い、では「なんまいだ」で行こうということになる。一同晴れて「なんまいだ」を唱えながら、最初は数珠を時計回りに回してみるが、なんだかしっくりこない。逆じゃなかったかと誰かが云う。それで今度は逆に回してみる。これだこれだ。昔、確かにこうやった。
鉦がカンカン鳴らされ、数珠は勢いよく回りはじめる。いやいやこれでは早すぎる。おらあ年寄りだで、手え追いつがねえ。息切れる。もう少しゆっくりすべえ。
「なんまいだーあ、なんまいだーあ、いやもう少しゆっくり、なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ……」
これでようやくペースがつかめて、落ちついて数珠を回せるようになったが、今度は銭を動かすのを忘れる。銭を動かして数える係を決めて、またやりなおしになる。
「なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ……」
念仏の合唱のなか、黒光りのする一本の数珠が、じゃらじゃらと音を立てて、一同の輪の中をめぐる。やっていることは、別にたいしたことでない。だが絶えず念仏を唱えながら巨大な数珠を回し続けるとなると、これが結構な労働で、数珠の重さがしだいに腕にこたえてくる。誰かが、銭二枚ずつ数えることにしたらどうかという。そうだそうだ、それがいい、とてもじゃないが、こんなこと長いこと続けていたら、時間もないし、くたびれてしまう。
「なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ、なーんまーいだーあ……」
念仏の合唱のなか、数珠がじゃらじゃらと音を立てて、一同の輪の中をめぐる。黒光りする蛇のように。わたしたちは、いまほんとうは太くて長い蛇を抱いて回しているのではないか? 黒々とした立派な蛇、あの太古からの蛇を……ナンマイダの合唱は一種の催眠効果を有し、瞑想状態を誘い、わたしはなにやらおかしくなりだした。頭がぼうっとしはじめ、自分が確かに声を出し、念仏を唱え、腕を動かして数珠を回しているのだが、その自分がなんだか遠くにいるような気がしはじめた。
そのときわたしの頭にふと、ひとり道ばたにたたずみ念仏を唱える虚無僧の姿が浮かんだ。その僧は、どこかの辻角に立っていた。どこか知らない場所の……いや、あれは辻のお地蔵様のお堂ではないか。この僧はすぐそこにいるのではないか。大都会の駅でこの虚無僧姿の男を見たときには少し異様な気がしたものだが、この田舎の、おそらく二百年も前から景観などほとんど変わっていないだろうと思われる、この農村の辻角には、虚無僧のような男が立っていても少しもおかしくはない。頭をすっぽり覆ってしまう深編笠をかぶった異装の姿も、ついこのあいだまで狐が人を化かし、巫女に祈祷させたりお札にすがったりして病を治していたようなこの土地では、少しも異様ではない。
むしろその姿は、この土地と深くつながっているもの、狐のお化けや歩き巫女や梵字の書かれた魔除けのお札と一体のもののように感じられる。わたしの家には、かつてそうしたお札を作って配っていたころ使われていた、梵字やお経を彫りこんだハンコがいくつも、古い箱にしまわれてあるのだ。そしてその箱は、わたしが近づくとまだ息をしている。それらのものはまだかつての力を失わないで、わたしをじっと見て云うのだ。おれの出番はまだなのか。おまえはまだおれたちを使わないか。
わたしはその虚無僧になんとしても近づきたいと思うが動けない。その僧が妙に懐かしいものに感じられて、自分にとても近しいもののように感じられて、わたしは思わず腕を伸ばし、その人に呼びかけたいと思うのだが、わたしの身体はここから動けない。
だがその人はもうすぐいなくなってしまうとわたしにはわかっていた。いまこの時を逃したら、もう二度とその人に会えないとわかっていた。わたしは訊きたかったのだ、どのような深い罪を背負って、あなたは遊行して歩くのか、どのような汚れを身に帯びて、あなたは常人の暮らしの外に出てゆこうとするのか。ああだがそれらはわたしのものだ、みんなわたしのものなのだ。どうかそれを置いていってくれまいか、わたしのところに。そうすれば、あなたは解放されるだろう、そしてわたしはまたひとつ罪深いものになり、また一歩彼岸へ近づく。どうかそれをここへ置いていってはくれまいか、あなたの魂をここへ置いていってはくれまいか。そうしたら、わたしがそれを食べてしまおう。それはどれほどわたしの腹を膨れさせ、満たすことだろう。
だがその虚無僧は、やはりどこかへ行ってしまうようであった。顔の見えないその僧は、編笠を深くかぶり直し、そのあらゆる地上的な絆を断ち切り、ただおのれの業だけを身に帯びたような、泣きたくなるほど厳しい、近寄りがたい立ち姿をふっとゆるめて、立ち去るそぶりをみせた。
どうか行かないでほしい、わたしはここに縛りつけられている、情けなくも動けないでいる。このわたしに気がついてほしい、わたしはここにいる、すぐそばにいる、どうか気がついて、行くのを待ってほしい。
そのときその僧が、ふとふり向いた。深い編笠に隠れて、顔かたちはまるで見えなかった。だが笠の編み目のあいだから、わたしはその人の目を確かに見た。そしてその瞬間、わたしはそれが誰だかわかったのである。
「はい、終わり!」
という声が突然響き、気がつくと、念仏の合唱はすでにやんでおり、婦人たちは数珠を回す手を止めていた。仕事を無事しおおせた安堵の笑みが漏れ、皆いっせいに「ああ」とか「ふう」とかため息をつき、それが念仏の漂う少々異様な空気を、どこかへ吹き飛ばしてしまった。わたしは明るい日の差しこむ、見慣れた集会所の中にいる自分を見出した。
ああ終わった終わった、くたびれだ、さあ、お茶っこ飲むべえ。婦人たちはいっせいに立ち上がり、数珠と鉦とを箱にしまい、その箱を隅に押しやり、テーブルを出してきて、慣れた手つきで紙コップやお菓子を並べはじめた。お湯が運ばれてきてコーヒーが配られ、袋菓子が手際よく分配される。
そうして、おそらく婦人たちにとって念仏などよりよほど大切なお茶飲みの会がはじまったが、わたしはなにやら不思議な心持ちで、日の光のなかでテーブルを囲んで座るご婦人がたを見まわしていた。
ご婦人がたの話は、確かに下世話なものが多く、大半がたわいない噂話であった。祖母や母が、こうした集まりを嫌うのも無理はなかった。が、わたしはそういうことを感じていたのではなかった。わたしはその人たちを、いまや自分と地続きのものとみなしている、というより確信している自分に気がついたのである。
わたしの目の前にいるこの人たち、このぺちゃくちゃおしゃべりをしながら笑い声を上げ、コーヒーをすすり、お菓子を頬張っている女性たちと、わたしはともに念仏を唱え、ともに数珠を回しあったのである。そのことによって、わたしたちはひとつの霊を呼び出した。この土地に祭られた霊、この土地の祭儀をつかさどる霊、この土地に住む人々の集団を、ほかの人々とは違うものとして選別し、その印を刻印する霊である。わたしはこの霊の存在をありありと感じた。そしてその霊が、いまや儀式を行ったわたしたちすべてのなかに入りこんでいるのを感じたのである。
わたしはこのとき、人を真実に相互に結びつけるものとはなにかを見たのであった。ある集団を、単なる人々の集まりから、自覚的な共同体、ないし秘密結社にまで高めるものを見たのであった。それはひとつの霊であった。土地の霊であり、自然の霊であり、祖先の霊であり、人の共働のなかに働く霊、人間の共働という現象によって呼び出され、力を受ける霊である。それはわたしたちが共働で捧げる儀礼を受けて、わたしたちの結束のために自己を解体し分化し、わたしたちひとりひとりのなかに入って働く霊となる。そしてそれは、わたしたちがひとつの分かちがたい共同体、ひとつの霊を分かちもつ人々の集団であることの印となる。
講は、否、有史以来のあらゆる共同体は、本来こうした霊の力によって成立しているのだ。かつての人々はそれをよく自覚していたから、この霊を定期的に祭るのを忘れず、そなえものを欠かさなかった。それは「われわれ」をほかのなにものでもない「われわれ」たらしめる根源的な原理であり、その結束の源であり、その印を各人の身体に刻むものであった。人間の共同体は、このような霊の力によって結ばれているために、一度共同体の一員となったものは、死ぬまでそこから逃れることができない。それは人間の都合で解くことのできぬ性質のものだからであり、もし誰かを追放しなければならない場合には、同じような儀式でもって、ふたたびその霊を呼び出し、その霊から切り離す作業を行わねばならない。人の生死や追放にまつわる儀式は、この霊の存在の自覚ゆえに生じ、行われてきたのである。
この霊こそは、人間の団結、連帯という目に見えぬものに生きた肉体と実感とを与えるものであり、人はそれを感じられてはじめて、真実に自分がほかの人々と分かちがたく結びついていることを知る。ただこの霊によってのみ、人は血縁関係や友情や愛情といった、本能や私的な心情を乗り越えて、まったく異なる人々と社会的な強固な関係を結びうるのだ。
わたしはなにやらめまいを感じた。念仏講がこれほどの力をもつものとは思わなかった。正直なところ、わたしはそれをただの地域行事と思っていたし、念仏なる名前がついているとはいえ、現代では誰も昔の人たちのように、切実な思いをもって仏教を信仰しているはずもない、子どもを守り成長を見守ってくれる地蔵菩薩への信仰は、医療や科学技術の前にすっかり敗れ去ってしまったに違いなく、ゆえに念仏講のようなものは、現代ではただ伝統なる名のもとに、形骸化され精神を剥奪されながらもかろうじて受けつがれている、あわれな死骸のようなものに過ぎないと思っていた。
ところが、それは決して死んではいなかった。あらゆる共同体の背後にあり、彼らを互いに結びつける霊、その結託に力と肉体とを与える霊は、あの古代の呪術の時代から相変わらず生き続けているのであり、人間社会の移り変わりなどでいなくなるようなやわなものではなかったのである。
同時にわたしはこのとき、自分がどうして結局教会に居つくことができないで、そこから抜け出してしまったかを理解した。教会に通っているあいだ、わたしは霊的なものを感じようと努力したが、かなわなかった。それは儀式を行うのが参加者でなく、聖職者だったからなのだ。儀式の背後で働き、人々を結びつけるこの霊は、わたしたちがその儀式に各自の肉体をもって関わり、参加するときに、はじめて本領を発揮するようである。ひとつの作業を皆で完成させたときにはじめて、この霊は真に生きてわたしたちの団結のために働き、わたしたちを相互に強力に結びつける働きをするようなのだ。
わたしはなにやらそらおそろしいものを感じながら集会所を出た。わたしが動くと、わたしの後ろを、横を、前を、その霊が一緒に歩いてくるのである。そして人々の中にもこの同じ霊がいるのが見えるのだ。こんなことは期待していなかったが、もうどうしようもない。この霊をわたしの身体からもぎ離すことは、もう人間などにできるものでない。
わたしは期せずして、土地の者になり、土地の霊を受けてしまった。家に帰る前に、わたしたちはみんなでお地蔵様の前で合掌して拝んだが、わたしにはお地蔵様が笑っている気がして仕方がなかった。
「おまえは今日、わたしの力を見たであろう。何百年もこの地に据えられたわたしの力を。地の力を、肉体の力を、霊の力を見たであろう。わかったか、この頭でっかちめ」
このときわたしは思い出したのである。幼いころ、わたしを連れてどこかへ行くとき、祖母は必ずこのお地蔵様の前で立ち止まり、手を合わせて拝んでいった。あるときわたしがなにを拝んでいるのか訊ねると、祖母はこう云ったのである。おまえが風邪をひかぬように、無事に大きくなるように、立派になるように、元気でいるように。
ときどきは、祖母はなにかお菓子を持ってきて、おそなえすることもあった。そんなときは、帰りにまたお地蔵様の前を通るとき、祖母は出がけに自分がおそなえしたお菓子をひとつ取りあげて、わたしに手渡し、食べるように云うのであった。お地蔵様の食べたものを食べれば、風邪をひかず、頭もよくなるというのである。
そのころのわたしは、なにも考えずにただお菓子をとって食べた。それはせんべいだったり、クッキーだったり、チョコレートだったりまんじゅうだったりした。だがわたしはなんというものを食べたのだろう。かつてわたしはこのお堂の横の木陰で休んだ。この辻で遊び、その前の用水路に石や枝を投げ落とし、ついでに自分も落ちてえらい目に遭い、近所の家の風呂を借りたりした。わたしたちはただ子どもであった。そしてそれだけで、このお地蔵様とその横の木と、この土地と人とそれらを支配する霊のすべてに守られていた。
わたしの唱える南無阿弥陀仏に、そのような深さがあったろうか。わたしの生き様に、そのような深みを生むなにものがあるだろうか。わたしはこのときただそれを恥じ、深く恥じたのである。そして自分が先ほど受けた霊の意味を、それがわたしに許されたことの意味を、わたしはいま問われ、生きるよう要請されたように思ったのである。
初出:2022/05/02「雪下」第二十三号