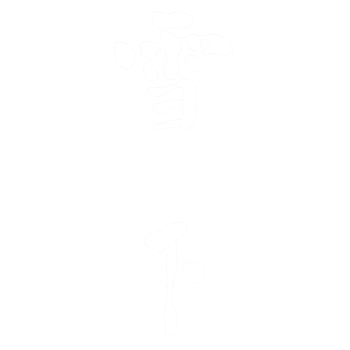久々の投稿だが、まだまだ中国にいて、最近、白川静の『漢字の世界』を読みはじめたが、その中に前漢時代に編集された百科事典的な書物である『淮南子』の一文についての解説があり、非常に興味深かった。二、三日前にちょうど『淮南子』を読みはじめたばかりだったのでなおさら興味深かったのであるが、ともかくその文章というのは、
「その昔、蒼頡(そうけつ:黄帝の史臣)が文字を発明するに及んで、天は粟の雨を降らせ、鬼魂は夜泣きした。伯益が井戸を掘るに及んで、竜は黒雲に乗って去り、百神は崑崙に移った。すなわち、智能がまさるにつれて、徳性は薄れるのだ」(戸川、木山、沢谷訳、平凡社『中国古典文学大系6』)
というものだ。これを白川は、
「老荘思想の立場に立つ文化史観である。天が粟をふらせたのは、その異変をあらわしたものであり、また鬼神が夜半に哭したというのも、人智が神工を奪うことを嘆くものであろう。……もはや鬼神の専制の時代は終わったのであった」
と解説している。白川静の本を読んでいると、古代の人々がいかに呪術的な思考に支配されていたかわかる。その痕跡は漢字という文字に生々しく残っていて、文字という漢字そのものも、文は人が死んだときに胸に入れる入れ墨をあらわし、字は一族に正式に迎え入れられた新生児を廟の中に置いて、祖霊に見せる儀式を示す。中国古代の人々は、人が世に生まれるのは祖霊を継承するためだと信じ、出生に際しては額に入れ墨してほかの霊に侵されることから防ぎ、この新生児が祖霊を継承するにふさわしいかどうか試すために川へ流して(流という字そのものが、川へ流されている子どもを示す)神意を確かめ、その子は成人に達してはじめて一人前と見なされてほんとうの名が与えられるが、この名という漢字がまた祭肉と祝詞を入れる箱をあらわし、命名の儀式をあらわしているのだという。
こんな時代においては、人というものはいかに他愛なく残酷で美しいものだったろうと思うが、現代においてなおこのように無為を貫き、鬼神に我が身を任せて生きることは可能だろうか。智能がまさるにつれて徳性は薄れる……人の智能が発達してくれば、もう降雨を司る竜も鬼神も用なしだというのであるが、面白いのは、竜や鬼神を奉ずることと徳性とが一緒くたにされているところである。徳は間違いなく敬いから生ずるが、敬うこと少なくなれば徳が減じるのは必然であって、こういう自然科学万能の時代になお天地を敬い、努めて理性を遠ざけておのれをなりゆきに任しておくという生き方を選択することは、ばかげたことには違いないが、しかしまったくの無駄でもあるまいと思う。
この発見をする少し前に、カトリックの坊さんに向かって、わたしはカトリックの信者ではないがカトリックのことは非常に尊敬していると力説する夢を見たが、カトリックの坊さんは実際に、キリスト教の侵入によって流刑に遭った古代の神々の寄せ集めという側面がある。カトリックの坊さんやローマ教皇を熱心に信奉することは、キリスト教という制度への信頼以上に、いまやいよいよ圧殺されつつある人間の古代的感性を満足させる側面があるに違いない。そしてその古代的感性の裏にあるものを注意深く見てゆけば、迷妄や迷信とないまぜになった、人間の生の姿というのがあるに違いないのである。文化を越え文明をまたいでそこへ還ることが、人にとって楽園への道行きでなくてなにか。