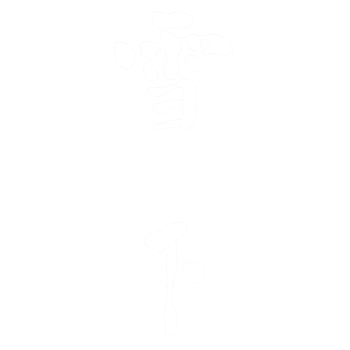十二月六日、早稲田松竹へ昔の映画を見に行く。大島渚特集をやっていて、「愛のコリーダ」と「戦場のメリークリスマス」をかけていた。どちらもはじめて見る。
「戦場のメリークリスマス」は戦争映画だが戦闘シーンは一切なく、日本人兵と外国人俘虜たちのやりとりから、男社会の最低のところから最高のところまでをえぐり出している。
デヴィッド・ボウイが英国兵俘虜の役をやっていたが、彼の物語は胸を打つものがあった。陸軍少佐セリアズは、パブリックスクール時代、成績トップで寮長をやっていたという、男社会に完璧に順応した人物である。彼には弟があったが、美しい歌声を持ち、いつも歌を歌っているような少年だった。だが弟はいわゆるせむしで、背中に大きなこぶがあり、そのことを人に知られるのを恐れていた。
おそらく入寮の通過儀礼みたいなものだと思うが、セリアズの寮には新入生を丸裸にしてみんなではやしたてる伝統があったらしい。弟もまたこの洗礼を受けることになり、彼は歌を歌うことを強制されたのち、丸裸にされて背中のこぶをさらしてしまった。だが本来この通過儀礼には、身体障害者は除外するという規則があって、その規則によれば弟は当然除外されなければならなかったのである。だがセリアズはそうした采配を振るえる立場にいながら、弟を参加させた。自分の身内は自分と同じように完璧な存在であってほしいと思ったからである。
セリアズは弟が男社会の残酷な洗礼を受けているあいだ、口実をもうけて実験室にこもっていた。弟は叫んだ、「兄さん、助けて!」
だがセリアズはその場にいなかった。その日以来、弟は歌うことをやめた。
俘虜収容所の所長ヨノイ大尉は複雑な人物だ。日本社会は元来男性性というものにそれほどこだわりをもたなかったと思うが、戦争だ徴兵だで突然極端な男性性を要求され、男社会の中に投げこまれて、日本人男子の多くは苦労したと思う。彼にはその苦労がにじみ出ているような気がする。いびつな、未成熟な、未発達であるゆえにどうしても極端に陥ってしまう、日本人男性にとっての男性性というようなもの、その矛盾、ばからしさ、哀しさ、しかしときに垣間見える崇高さ、というようなものを、彼は体現している。もとより男性性は硬直しやすい、そして極端に陥ってしまいやすい。そのようなものがまともな文化的洗練も訓練も受けないで解き放たれたとき、それは暴走しいたずらに権柄ずくになり、本来持ちうるはずの合理性や秩序正しさとは真逆のものになってしまう。
ハラ軍曹のように、理不尽に権威を振りかざし暴力を振るう男の姿は、おそろしいというより滑稽である。外国人俘虜相手に粗暴なふるまいを続けるハラ軍曹には、なんだか哀愁が漂っている。彼にはきっと男らしさがどういうものかわからないのだ。どうしたら集団の規律を維持することができ、秩序を維持して統治することができるかなんてことは、彼にはわかりようがない。その原理を、彼は原始的な威圧と暴力とに求めるしかない。威圧的で暴力的な男は人に隙を見せることができず、弱みを見せることもできない。それに耐えられなくなったとき、軍曹は飲んだくれて、急に気前のいいサンタクロースになってしまったりする。
ヨノイ大尉ははじめ、それほど凝り固まった将校ではなかったはずである。彼の手綱はきつく締められていたけれども、それでもまだどこかゆるみがあって、俘虜たちには少々の余裕もあったはずである。だがジャック・セリアズ少佐が収容所にやってきたことで、彼は変わってしまう。かつて弟の歌を殺したセリアズ少佐は、花を摘んできて死亡した俘虜のベッドにまいたり、みんなにクリスマスの歌を歌わせたりと、不思議な魅力を備えた男として、ヨノイの男性的な秩序への挑戦者として現れる。ヨノイ大尉は彼に惹かれ、同時に彼を恐れる。ヨノイはしだいに常軌を逸した理不尽な命令を外国人俘虜たちに連発するようになるが、それが極まったとき、セリアズはこうつぶやく。「おれに歌が歌えたら」と。
この台詞をデヴィッド・ボウイが云うことには深い重みがあるが、セリアズは結局見せしめのように穴埋めにされて処刑されることになる。しだいに弱ってゆく中で、彼は弟の幻を見る。花が咲きみだれる美しい生家の庭で、弟が歌いながら花に水をやっている。セリアズが兵士姿で近づいてゆくと、弟は彼を温かく迎え入れ、謝る彼に許しを与えて、早く家に入ろうと云う。かつて自分が虐げ抹殺してしまったものと、セリアズはようやく再会したと思ったのだが、ほんとうは前から一緒だったのだ。彼がヨノイに、人間の真に人間らしい武器で抵抗を試みていたときから、弟は彼の中で歌っていたのだ。ただ本人が、そのことに気がつかなかっただけである。
ところでハラ軍曹役をビートたけしが演じているが、彼にはやはり、日本芸能の歴史がみんなこめられている気がしてならない。聖であり同時に賤であった芸能民たちの歴史が、貧民であり同時に言祝ぐ神であった彼らの相が、さすらう者たちがもたらす笑いという非日常の、聖なるものの相が、あるように思う。
帰宅してふと翁の面を手にとって眺めながら、映画の最後にアップで映されたビートたけしの顔を思い浮かべ、つくづくその相似を思ったことである。