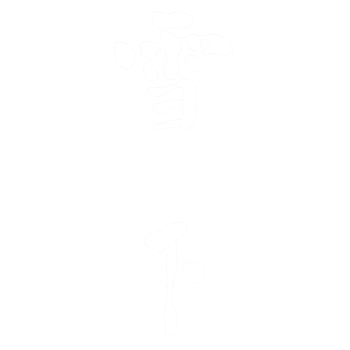かつてあったことは、これからもあり かつて起こったことは、これからも起こる。太陽の下、新しいものは何ひとつない。
見よ、これこそ新しい、と言ってみても それもまた、永遠の昔からあり この時代の前にもあった。コヘレトの言葉、第一章九節から十節(新共同訳)
「なんという空しさ なんという空しさ、すべては空しい」からはじまるコヘレトの言葉が厭世的かどうかはひとまず措くとしても、この言葉に真実を感じるかどうかでその人がどういう傾向を持った人なのか、あらかたわかるような気はする。
小川国夫は、『聖書と終末論』のなかで、人は前に進もうとするとき過去に戻るのだという趣旨の発言をしていて、これも興味深い。いま手元に本がないので正確な引用ができないけれども、小川は自身の少年時代のエピソードを挙げて、人生に危機が訪れるたびに、人は子どものころに感じたあのうれしさ、あのよろこび、というようなものに立ちもどってみずからを立て直そうとするのではないか、人は過去に必要なもののすべてを持っていて、そこからすべてを引きだしてくるのではないか、という内容だった。
先のコヘレトの言葉もそうだし、小川国夫の言葉もそうだけれども、わたしのように新しいということには常に反感しか持たないタイプの人間は、要するにこうした感じをもって生きているのだ。生まれる前、わたしたちの魂がつくられたとき、わたしたちは神の手の中にいて、神の完全さのなかでぬくまっていた。そしてこの世に出てくる段になって、神はたぶんレテ川の水をひしゃくで一杯わたしたちに飲ませ、みんな忘れさせてしまった。神の記憶も、その叡知も。人は神を知らないのでなく、叡知を知らないのでもない。ただ忘れているだけだ。人は獲得するためでなく、思い出すために生きるのである。
すべての出会いが新鮮さでなくなつかしさを、驚きでなく郷愁を、かき立てるという生き方のことを考えてみてほしい。新しいものに立ち向かうには知力も体力も必要だが、なつかしさや郷愁にひたるなら、必要なのは繊細な情趣を感じとることのできる鍛えられた感受性だけである。思うに、ものを書く人間は、ありとあらゆる人や物にたいして、なんだか無性になつかしいような気がしてしまう人間のことをいうような気がする。誰かの本を読んでいて思うのは、こういうことは自分だってとうの昔に考えて、書けていなくてはならなかったはずだが、なぜ思いつかなかったろう、ということだ。わたしはこの手触りを、匂いを、雰囲気を知っているし、確かにどこかで感じたことがあり、それを言葉にしようとした瞬間すら、確かにあったはずなのだ。だがそうしなかったということは、要するに、それがわたしの限界であり、鈍感さのあかしであろう。
こういうことを書くと、その背後にひそんでいる尊大さの匂いに鼻持ちならない気がする人が当然出てくるはずである。たぶん、その通りなのだろう。古典作品をつかまえて、この言葉づかいを、この定義を、なぜいままで思いつかなかったろうなどと考えるのは、傲慢さと愚かさのしるしである。だが、こんなことなら自分だって考えたことがあるとか、この程度のものなら自分にも書けそうな気がすると人に云わしめたとき、その作品はもっとも成功したことになるとわたしは信じる。どんな本を読んでいたって、これがわたしの云いたかったことなのだ、という言葉がひとつふたつは必ず出てくるはずである。出てこないなら、それは作品が本物でないか、自分が本物でないか、どっちかである。
感銘とは喚起であり想起であり深い共感のことである。ほんとうの意味でオリジナルなどというものは、この世には存在しない。ほんとうの意味で新しいものも、この世には存在しない。そんなものは存在し得ない。わたしたちの経験はすべて、共通の基盤と個性とのあやうい綱渡りのうえに成りたっている。このことを一度も考えてみたことのない人は幸せであるが、個性的な、新奇な感じを出そうとしてなされる努力が総じて浅ましい様相を呈してくるのはなぜかという問題は、このことをよく考えてみればわかるはずである。オリジナルという言葉に非常に謙虚になって考えてみれば、そんなものが自分に生み出せるわけのないことはすぐにわかるはずだが、ものごとの表面しか見ない浅薄な精神だけが、そんなことでおたついて、なんとか自分はひとつうんと個性的であろうなどと大騒ぎするのだ。もう一段深いところへ降りていけば、個性などというものはきわめて地味な、だがおそろしいような深みと鋭さを持ったものであることがわかるはずなのだ。そこまで降りていかなければ、個性は真実に個性たり得ない。
新奇さは浅はかさや狂騒と紙一重である。そのものですらあるかもしれない。このことは何度云っても足りないくらいだ。単に新しさと云った場合だって、もうずいぶんあやしい。このあやしさの匂いに薄々気がつくようになってきたころに、たぶん人はほんとうの意味で歴史の価値を、そして古典の価値を知るようになるのだろう。いまわたしは吉田兼好じいさん(となぜかわたしは親しみをこめて呼んでしまうが)がこんなふうなことを云うとき、心からうなずいてしまう。
ひとり燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなうなぐさむわざなる。(第十三段)
何事も、古き世のみぞしたはしき。今やうは無下にいやしくこそなりゆくめれ。(第二十二段)
若さというものに、耐えがたい羞恥を覚える人種というのがいるものだ。若いことと新しいことはどちらも醜い。昔から、早く四十くらいになりたいものだと思っていた。そのころになれば、わたしはようやくいくらかもののわかった人間になるだろうと漠然と感じていた。そろそろ四十の声も近づいてきたいまは、四十になったところで、どうもなにもおぼつかないような気がしはじめている。相変わらずなにも理解していないし、世事には疎く、いまこの世界でなにが起きているのか、てんで見当もつかない。ただ昔のもののみが、むやみに自分の肌に合い、自分とひとつ心であるように感じられる。古びて、さびれて、失われていったものだけが。この世において死んだものだけが。
だがそもそもわたしは過去である。過去が現在と出会う場がわたしである。わたしはこの存在のうちに、わたしに連なるすべての人間を抱えこんでいる。わたしの血の中に、すべてはある。この血の中には、宗教家がおり、画家がおり、狂人がいて、愚にもつかないぼんくらも、血気はやって若死にした者もいる。要するに、ありとあらゆる人間がいる。ありとあらゆる時代を生きた、ありとあらゆる人間が。わたしはその集積であり、その総体である。ここにもの書きの武器がある。わたしはうずたかく積まれた死者の山の上に立っている。わたしは死者である。わたしがいま生きているのは、まだ死んでいないというただそれだけの理由であり、わたしと彼らを隔てるものは、ただそれだけである。
いまを生きる根拠は、わたしのうちに眠るこの死と過去にある。生は、自分のうちに眠る過去と死とを、見つけていくためにある。あなたのすべての能力は、ただかつての生者たちの積み重ねからのみ生まれ得たものだ。あなたはそれに、ほんの数十年分の成果をつけ加えるに過ぎない。そしてそののち、静かに死者の列に加わる。この安堵を知らないのは不幸だ。これを感じないことは、おそろしく孤独なことだ。
創作に従事するにあたって、自分の力の源がどこにあるのか考えてみるのは有用なことである。特にもの書きの力の源というのは、身につけた知識だの書く技術の訓練だのとはちょっと別のところにあると気がつくことができたなら、そのときたぶん少しものを書くということがどういうことか、わかってくるのではないかと思う。自分という人間の足場がどこあり、自分に与えられた力を養うために必要なことはなんであるのか、というようなことが。ただわたしの努力によって養った能力を、わたしがひとりで抱えていまここにいるなどと思うなら、もの書きは孤独でひとりよがりなだけの存在であって、書斎のウジ虫の域を出ないだろう。われわれはせめて、ハエくらいにはなりたいものだ。書斎を出ることはかなわないにしても、飛びまわる翅くらいは持ちたいものだ。
ウジ虫は屍肉を食らい、われわれも死んだものを食さねばならぬ。われわれの栄養は死にあるのだ、生の中にあるのではなくて。新しい日に、わたしは古い土を掘りかえす。光に当て、乾かして、また用いるために。エッサイの株からひとつの芽が出て、その上に主の霊がとどまるまでに、エッサイの株はどれほどのものを、古びた地の堆肥から吸収したことだろう。どれほど多くの血、どれほどの土の実り、どれほど多くの男と女の、よろこびと悲しみ。わたしたちは、古びた土を食らい、そこからなにかを生みだすために、日々生きるのだ。
初出:「雪下」第八号