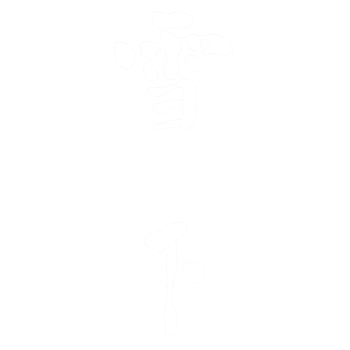「へへへへへ、どうも、こいつはまずいところを見つかっちゃったな」
悪魔がへこへこした態度で出てきた。悪魔はいつも寒いのだそうで、地上をうろつくときには、定期的に火にあたらないと凍えそうな気がするのだそうである。この日もちょうど、わたしがマッチかライターか持っていて、なにか燃やしてくれないかと期待するような目でわたしを見た。だがわたしが知らんぷりをしているので、ほどなくあきらめたようにちょっと肩をすくめて、部屋の隅に腰を下ろした(そこが悪魔の定位置である)。
「あなたはあれですね、お怒りですね。なんでかというと、わたしがまた神を騙ったからですね。いつものようにですね。でもねえ、わたしに云わせりゃ、引っかかるそっちが悪いんだ。わたしゃ、あなたにはちょっとした親しみを覚えてますんでね、なにしろあなたはほかの信心持ちの連中と違って、わたしを目の敵にして追っ払ったりはしないもんだからね。まあそれだもんだから、わたしも調子に乗ってついやりすぎたりするんだが……おっと、そりゃあいけない、あんた、いまさら信心深い連中の真似をしようたってそうはいかんよ。いいですか、聖水だの十字架だのはだね、そいつが本気でそれを信じている場合にだけ、わたしらを追っ払える力をもつんですよ。あんたみたいに、神さまは信じちゃいるが同じくらいわたしのことも信じてるような人にはだね、ま、どだい無理だろうね、わたしを追っ払うなんてことは」
わたしは腹が立ったが、悪魔の云うことももっともだと思ったので、椅子に座りなおし、そばにあった聖書をわきへ押しやった。
「へへへ、そうでなけりゃ。だいたいあんたは日ごろから信心にあまり熱心なほうじゃないね。わたしは知ってるんだ、そういうことを。まあ話を戻しましょうよ。試練について云々って話にね。ヨブの話は覚えてますね?」
わたしは「そうくると思った!」と叫んだ。
「まあまあ。せっかくわたしがこうして来たんだから聞きなさいよ。あの話はなにからはじまった? あの清廉潔白で、きわめつきの信心バカのヨブが……おっと失礼、だがあんたもバカだと思ってるだろ、少なくとも常軌を逸しているってことをさ、だってそうじゃないですか。おかしいでしょう、人間の分際で、神を心から信じる無垢な正しい人で、悪を避け、他人の悪の心配までし、おまけに大金持ちだなんてさ。けしからんよ、実際。
それで、そのヨブのことを神さまはわれわれの親分様のサタン様に自慢したわけだ。ヨブのような者があろうかってね。それが間違いのもとだね。挑戦を受けて黙ってるサタン様じゃないからね。『なにをおっしゃいますやら、ヨブがあなた様を敬っているのは、あなた様がヨブに目をかけて、財産や一族を守ってやっているからじゃありませんか。そいつが損なわれてごらんなさい、ヨブはきっとあなたを呪いますからね』とね……うまい理屈じゃありませんか。
神さまはこいつにまんまと乗っちまったんだね。そんなら実際にやってみろ、ってんで、ヨブを好きにする許可をサタン様に与えた。いいですか、そういう存在なんですよ、神は。そういうことをしちゃうんだ。人間を勝手気ままに試したりわれわれの好きにさせたりというようなことをですね、やっちゃうんだ。それだのに、あんたらはお人好しだねえ、それをありがたがって、ますます神さまを好きになると来てる。ぶん殴られるほどに亭主が好きになる女房みたいだな、最近はそういうやつが減ってきたけど。時代の変化ってやつかね。昔はよかった。世の中がもっとはっきりしてたからね。いまじゃなにがなんだか、すっかりわからなくなっちまった。やりにくいったらない。受難ってやつだよこれは……」
われわれは少し一緒にしんみりした。わたしも悪魔の云うことがよくわかったからである。
「だけどもねえ、実際、こんなこたあ、あんたに好意を持ってるから云うんですよ。こんなこと、普通は云えませんや。だってさ、人が神さまへの信仰をなくせば、それはわれわれが力を行使する余地も同時に奪うってことになるわけだからね。われわれはひとつなんだ、実際には。だけど、さっきも云ったが、あんたはわたしに結構よくしてくれたからねえ。悪魔が悪いんじゃない、自分が悪いんだってんで、ずいぶんわたしをかばってくれたっけ。
だからねえ、忠告しときますよ。おやめなさいって、神さまなんて御仁を当てにするのは。同じようにだね、わたしとこんなふうに仲良くするのもおやめになったほうがいいね。どっちも結局、変わりゃしないんだ、わたしに云わせりゃあ。ただあんたがてんてこ舞いするだけで、それで神さまは悦に入る、われわれはほくそ笑む。そんなもんですよ。だからあんたはまあ、あんまりわれわれに煩わされないこったね。それが一番ですよ」
「……といってもねえ」
長い間のあと、わたしは書き損じの紙を集めて火をつけながら云った。悪魔が身を起こし、部屋の隅からいざって火のそばへやってきた。そうしてうれしそうに両手を火にかざして暖めはじめた。
「いいですか、わたしは生まれてこの方あなただか神さまだかに煩わされっぱなしなんですよ。それをいまさら、そんなことできますかねえ。あなたとこうしてお話もしない、神さまは当てにしないなんてことが」
「ま、難しいのはわかるね」
悪魔はゆっくりとうなずいて云った。
「だからわたしも、なにも無理してやれなんてことは云わないですがね。ちょっと日ごろの感謝ついでに云ったまでで。こりゃほんとは内緒なんだが、火のお礼に教えときますよ。悪魔が恩知らずだなんて思われるのはしゃくだからね。われわれはねえ、黙ってることだってできるんだ。あんたさえその気になりゃあ、われわれを黙らせとくことだってできるんだ。なにしろわれわれの存在は、まったく人間の側の交感能力にかかってるんでねえ。あんたがそいつをふいと切っちまう。すると、われわれはもうあらわれないってなわけですよ。したくてもできないんだ、あんたがわれわれに合わせてくれないんじゃあね」
「……そいつはなんだか寂しいなあ。神もなし、悪魔もなしの世界とはね」
わたしは頬をなでながら云った。
「なにごとも寂しいもんですよ。なにかをやるも、やらないもですね」
われわれはしばらく黙りこんで、燃える火を見つめていた。悪魔は火の前で手をこすりあわせ、次いで背中を暖めたが、それがすむと、出ていった。
初出:2021/04/03「雪下」第十号 前後を大幅に省略してある。