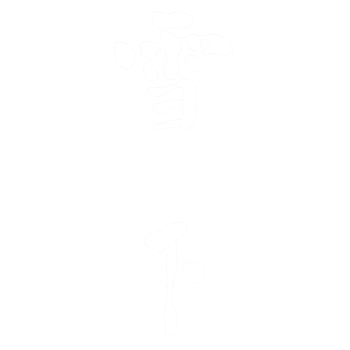二十九日の夜中、猛烈な胃痛で目が覚めた。焼けるように痛いというのはこのことで、胃が痛いどころではなく、背中まで痛い。じくじくと猛烈に痛い。食べ過ぎたのだろうかと思って胃薬を飲んだがおさまるどころではなく、よけいひどくなってきた。ちょっと感じたことのない種類の痛みで、たいていの痛みなら我慢できる自信があるがこれはどうも耐えるどころでない。呼吸が浅くなり、痛みで汗をかいてきた。
布団の中でしばらくうなっていたら、ふと、夕食にサバの押し寿司を食べたのを思い出した。そいつだ! わたしはひらめいた。これがうわさのアニサキスではなかろうか?
アニサキスは魚についている寄生虫で、魚を生で食べるとうっかりまだ生きているやつを食べてしまうことがあると聞いていた。弟が一度サーモンでえらい目に遭ったことがあると云っていたのを思い出し、尋常でない痛みを発している自分の胃の状態を鑑みて、きっとサバに虫がいたのだと思った。
調べてみたら、アニサキスは酢や醤油くらいでは死なず、サバ寿司にいることもあるらしい。強烈な胃の痛みを引き起こすのが特徴で、痛みの原因は、アニサキスが胃酸でもだえ苦しみ、逃れようとして胃壁に噛みつくからだと書いている記事もある。おのれ、とわたしは思った。だいたい、大手回転寿司チェーンから買ってきたサバ寿司はちっともおいしくなかった。酢飯が異常に甘く、サバもなんとなくべちゃべちゃしていて、そもそもあまり青魚が好きではないのになぜあんなものを食べたのか、自分の食欲のいやしさにつくづくげんなりしたけれども、とにかくじっとしていられないほど胃は痛むのである。
細長い寄生虫が、わたしの胃の中で七転八倒し、断末魔の悲鳴を上げているさまをわたしは想像した。末魔というのはサンスクリット語マルマンの音写で、人体の急所のひとつであり、それを断つとものすごい痛みとともに死に至るらしいが、わたしのこの尋常でない痛みはすなわち寄生虫のいままさに感じている死に際の痛みのように思われて、わたしはあわれみと腹立たしさと苦しみとでちょっとわけがわからない気分だった。
わたしはのろのろと布団を出、母の寝室へ歩いて行った。そしてわが寄生虫いままさに死なんとすの状態であることを伝え、こいつはちょっと我慢できそうにないが、どこか夜間の救急外来をやっている病院があるだろうか、と訊ねた。
母はわたしの苦しみが尋常でないらしいことを察し、すぐに父を起こし、救急をやっている病院にわたしを連れて行くように云った。父もまたわたしの様子がただごとでないと思ったらしくて、すぐに着がえをはじめ、わたしもうなりながら着替えて(どうも、あまりにも痛みが激しいとき、人間は自然にうなってしまうものらしい)、すぐに車で病院へ向かった。
とはいえ田舎のことであるから、救急をやっている大きな病院へは車で三十分くらいかかる。すでに夜中の一時に近く、信号はどれも正常な運転をやめて、赤か黄色に点滅していた。わたしはところどころにある街灯の明かりや、点滅する信号を見ながらうなっていた。ほかに走行している車は一台もなく、父は九十キロ近いスピードを出していたと思うが、まわりに目立つ建物もなく、ひたすらのんびり田んぼが広がっているだけの田舎道では、どんなに急いでもあまり速度が上がっていないように感じられた。スピードというのは、ごみごみした場所においてはじめて感じられ、意味をもつもののように思う。
病院へ着くと、受付で痛む胃を押さえながら問診票を記入し、保険証を出し、診察室の前で待った。あたりには誰もおらず、明かりが煌々とともっているだけで静まり返っていた。少し待たされた。診察室のわきの壁に大きな張り紙がしてあり、「救急を利用される患者様へ」と書いてある。なんでも、近ごろ必ずしも急を要しない診療のために、夜間の救急外来を利用する方が非常に多くみられる。こちらとしても患者様のために万全の態勢で臨みたいが、地方の医師不足は深刻であり、日勤をこなしたのちに夜勤の当直に当たらねばならない医師の疲労もたいへんなものである。ついては、救急外来を利用する前に、それがほんとうに急を要するものなのか、患者様ひとりひとりがいま一度よくお考えの上、ご判断を願いたい。
こういうことを書かれると少し考えてしまうが、人間の心理として、どうしても夜になると不安が強くなり、正常な判断力が失われる傾向があるのは致し方ないことである。夜中に子どもが高熱を出したりなどしたら、ことは一刻を争うように思われてくるだろうし、成人であっても夜中に猛烈な痛みに襲われたら、これはまずいかもしれない、死ぬかもしれないとつい思ってしまうのは止められないことだろう。
現にこうして自分も救急を受診しているわけだが、それはやっぱり痛みが尋常でないからであり、経験したことのない事態に遭遇しているから判断のしようがないのである。わたしたちは、体と直接意思の疎通ができるわけではない。体がなにを云っているのか明確に理解できるわけではない。体や心という現象の前に、言葉と経験とに立脚せざるを得ない理性は、そもそも多く無力であるのだ。これは確かに矛盾である。体という、わたしたちが決意し、決定し、行動するプロセスとはまったく別の範疇に属するものも、やはりわたしたちのものであり、わたしたちに責任がある、ということは。
しばらく経ってから、ようやく診察室のドアが開き、看護師が顔を出した。わたしは中へ入って行き、若い男性医師の診察を受けた。この医師が、少なくとも内科や消化器を扱うような医師ではないらしいことは話しぶりですぐにわかったが、ともかくも、医師は応急処置として痛み止めの点滴を打つという。
わたしは広い夜間救急治療室のベッドのひとつに寝かされ、点滴をされた。あたりにはベッドが八台、四台ずつ向かい合わせに並んでおり、薄いピンクのカーテンで仕切られている。点滴は昔から苦手である。痛みはまだ去らない。わたしはぼんやりと天井を眺めて時間をつぶすよりほかなかった。
しばらくすると、あたりが急に騒がしくなった。急患が運ばれてきたようである。人がばたばたと走り回る音が聞こえ、ストレッチャーが運ばれてくるがらがらという音が聞こえた。「Mさん、わかりますか? 聞こえますか?」「いま血圧は……」「ナントカを何フラッシュ……」
わたしはカーテンで囲まれていたために、なにが起きたのかは見ることができなかった。そのうちに、患者は検査かなにかのために別の場所に運ばれていった。そして今度は家族らしい人たちと医師との会話が聞こえてきた。どうやら、急患の男性は、今朝階段から足を滑らせて落ちたのだが、特になにごともなく、寝るまでぴんぴんしていたのだという。ところが、どうも様子がおかしいので、救急に電話をしてここへ運ばれてきた、ということのようであった。
そうこうしているうちに、患者がまた運ばれてきた。その人はいまは大きないびきをかいていた。昏倒するとそんなようないびきをかくというようなことを、前にどこかで読んだことがあるのを思い出した。「Mさん、聞こえますか? わかりますか?」看護師がふたたび呼びかける。男性はどうやら、急速に意識を失ってしまったようである。脳出血を起こしており、意識障害と呼吸障害が出ている、というような穏当でない話が聞こえてくる。
今日の当直医は、不運なことに、内科医でも外科医でもなさそうで、まるで畑違いの仕事を余儀なくされているらしい。たぶん、皮膚科とか耳鼻科とか、そんなようなのが専門の医師なのだろう、誰かに電話で指示を仰ぎはじめた。事態は深刻なようである。急患のMさんは、脳出血で死にかけているのだ。
わたしはMさんが気遣われてならなかった。いま、自分のすぐ横に、生死の境をさまよっている人間がいる、という事実は、わたしをむやみに厳粛な気持ちにした。頭を打ったら油断しないほうがいいという話は聞いていた。頭を打って何日もたってから、急にばったり倒れて死んでしまうこともあるという話を、これもまたどこかで聞いたことがあった。人間の体というものは、それほどまでに人間の思考から離れて自律しているのである。そしてわたしたちは互いに相手のことがわからない。理解するための共通の言葉を、われわれは持っていない。どんなに注意しても、勉強しても、わたしはわたしの体というものがなにを訴えているのかを、ほんとうには知ることができない。
それも腹立たしいことだが、いまMさんは生死の境をさまよっているのに、わたしがそのこととは絶望的なまでに無関係であることも腹立たしいことであった。Mさんは生きるか死ぬかの瀬戸際にあるが、わたしは単に胃が痛いので痛み止めの点滴を受けているだけの、少なくとも圧倒的に生命の存続を保証された人間である。その落差が生じさせずにいないやましさや恥ずかしさというものを、わたしはいったいどうするべきであるか。理性的に考えれば、救急を利用する権利はすべての人にある。わたしにもあり、急患のMさんにもある。われわれは互いに、その権利を行使しているに過ぎない。だからわたしがやましさや恥ずかしさを感じる必要は、ほんとうはどこにもないわけである。
だが、ほんとうにそうか? わたしはMさんのように、生命の瀬戸際というところまで来ているわけではない。わたしは単に痛みに耐えられなかったのであり、痛みからの解放を求めてやって来たにすぎない。そのこととMさんに生じている事態の深刻さとは、やはり比べものにならないことだ。だが、それにも関わらず、わたしたちはやはり同じ無知、同じ無明から、この夜中に救急へ来ているのだ。わたしもMさんも、体というものが発する信号を、そのなかで進行している事態を、適切に把握できないからこんなところへ来る羽目になったのである。そういう意味では、どちらも同じあやまちに陥ってしまったのだといえる。この無明、この愚かさ、このわけのわからなさ、この不安、この根源的な無知。そしてそれらすべてのわけのわからないことの先に待ち受けている、死というさらにわけのわからないものの恐怖。
気づくと、わたしは心の底から、Mさんが助かってほしいと願っていた。神に仏に祈っていた。それは、そばで人に死なれたら後味が悪いとか、そんなくだらないことではなくて、自尊心の匂いのぷんぷんする優等生ぶった感情からでもなくて、もっとずっと単純で根源的な感情であることに、わたしは気がついた。それは非常に自明で単純で、自我という混迷の暗がりの中から、なにか太陽のようにさしのぼってきたように思われた。それは生命に対する執心などというものよりも、もっとはるかに澄んだものだった。それは生命のもつ明るさそのものから自然に輝き出てくる光であり、生命が生命自身を謳歌するときに発せられる、子どもが無心に遊ぶときに発せられる、あの輝きの中から出てくるのであった。その輝きこそが、花がしおれたときに悲しむのであり、生き物の死を見て涙するのであり、同胞の死を悼むのであり、それを最後の瞬間まで引き伸ばそうと苦闘するのである。その輝きを、わたしは見たのだった。
あるいはこの輝きのことを、人はほとけごころと呼んだのかもしれない。かつて釈尊が云ったように、この生は確かに苦である。生きることは実に苦であるし、むくわれない、はかないことの連続である。その考えにひたむきに傾倒してゆけば、生などないほうがいいのであり、この世界はひたすらやりすごし耐えしのぶべき濁世ということになるだろう。だが同時に、わたしたちの生命の中には、もっと単純な、生命そのものの持つ明るさや輝きがあるのであった。そしてそれと体とは不可分のものなのであった。なるほど体は病み、痛み、死をもたらすけれども、それはまた同時に生命の不滅の輝きを宿しているのでもあった。われわれは有限であるけれども無限なのであり、かぎりのある存在であるゆえに永遠でもあるのだった。それはわたしのなかにあり、Mさんの中にもあり、そのほかすべてのものの中にもあるのだった。そうであるかぎり、やはりわれわれが生きてあることは、生命のうたう歌そのものなのである。それがひとつ失われれば、すべてのものはその喪失を悲しみ、新しくひとつが生まれれば、すべてのものがその誕生を喜ぶ。それはわれわれの理性ではなくて、生命の理屈である。われわれは人権などといういささかあやふやな概念をこねくり回さないでも、この生命の理屈に立脚して安心していることができるはずである。それができないなら、その人は少し頭でっかちになっているのであり、同時に身体への敬意を失っているということになるだろう。
わたしの点滴は、ほどなく終わってしまった。そのころには、胃の痛みは、痛み止めのために消えていた。だがわたしは自分の胃がまだ痛みを訴えていることを感じていた。痛み止めが切れれば、痛みがふたたび襲ってくるだろうということがわかっていた。だがMさんのこともわたしの胃のことも専門外らしい当直医に、これ以上のことを求めても無意味であることはわかっていた。医者は痛み止めの薬をくれ、わたしはまだ大いびきをかいている、予断を許さないらしいMさんを残して治療室を出ていった。
翌朝、まだじくじくと痛む胃を抱え、母に連れられて消化器内科の開業医のところへ行った。胃カメラを飲むことになり、なにやらずいぶん苦しい思いをして胃の中を診てもらったが、医者は困ったような顔をして、なにもないねえ、と云ってわたしに胃の中の写真を見せてくれた。ごく小さなポリープがひとつあるきりの、すこぶるきれいな黄みがかったピンク色の胃壁がそこにあり、血液検査の結果も、百点満点の超健康優良児である、とのことだった。
「うーん、まあねえ、生ものというのは、それについている細菌とかそういったものが、いろいろな反応を引き起こすこともあるから……まあ、生食には気をつけてください」
医者はそう云うと、わたしに退出を促すように、パソコンの画面に向きなおった。わたしは拍子抜けしたような、はじめからこうなることがわかっていたような、なんだか不思議な気分で診察室を出たのである。
胃の痛みは、それからしばらくすると、なにごともなかったかのように消えてしまい、わたしには二回の診療あわせて二万円近い領収書と、胃カメラで写した胃の画像だけが残されたのだった。人生には、こんな奇妙なこともときどきあるらしい。
初出:2021/05/31「雪下」第十二号