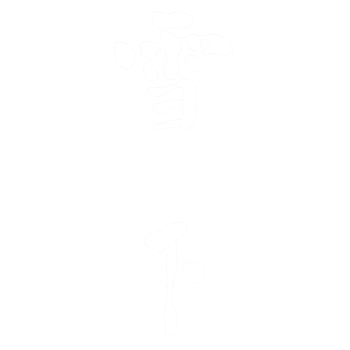実家は明治期に仏教から神道へ変わったので、家に神殿があって、薄暗い部屋に真っ黒な木板を組んだ祭壇があった。部屋の四隅は暗かった。祭壇の奥も暗かった。四隅の暗がりにはなにかが住んでおり、祭壇の暗がりの奥にはなにか絶対的な、ほかのあらゆるもとは違った存在がいるのだった。その存在はわたしを見つめていた。わたしはその存在と語りあうことを日課とした。
神とは語りあうことができる。われわれはオデュッセウスがパラス・アテナと語るように神と語ることができる。あるいは神の使者と語ることができる。神はわたしを打ちのめすときわたしを愛する。わたしが罪を犯すとき神は喜ぶ。もしもいかなる不幸とも罪とも無縁な魂があるのなら、その魂はこの世にいるべきでなく、神を目指す道において閉ざされているというべきだ。この世において神と語るためには罪と不幸とが必要である。悲劇が必要である。それらはふりかえってみれば、みんな喜劇であるのだが。
これ以上なにを語ろうか。わたしの喜劇を語ろうか、わたしが生きるこころみにおいてつまずき続けていることを語るべきだろうか。そしてあなたに同情やあわれみを乞うべきだろうか。確かにわたしは人の云う意味で生きたことは一度もない。衣食住への欲求や金銭への欲求において生きることが生きるということであるならば、わたしはそれらのものから遠い。わたしは実にこの世から遠い。だがわたしはここにおり、なんの因果か、おそらく罪の深さのためであろうが、神がここへわたしを置いたのである。であるからして、わたしは生きねばならぬ。
だが生きねばならぬとはなんであろう。存在の開始はほとんど暴力的なことがらではなかろうか。だから、自分の存在を生み出したことへの責任を問うて両親を訴えるというようなことをする子どもが出てくる。わたしにはこの気持ちがわかるが、それは人間というものに対してやはりあまりにも厳しい見方だろう。われわれが存在するのは弱さのゆえであろう。われわれが存在を開始するのは弱さのためであろう。人間的なもろさ、ひとりよがりの苦しさ、孤独の耐えがたさ、強烈な劣等感、癒えることのない存在の悲しみのためにわれわれは存在するのであろう。悲しみのためにわれわれはともに存在する仲間をもとめ、そしてさらなる傷と孤独を増し加えるであろう。
それは喜劇に見える。滑稽なうえにも滑稽な、愚かしい迷いに見える。人の営みはおそらくすべてにおいてこの喜劇の刻印を免れることができない。無明という言葉の意味をわたしは考える。だがそれは神のしるしであろう。神が人の額につけた印であろう。それゆえにわれわれは滅びることなく生きのびている。愚かしさに愚かしさをつけくわえながら。