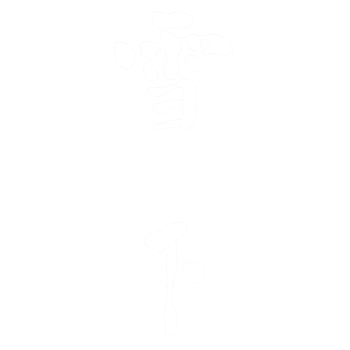わたしの生まれは秋田の横手だが、先祖は江戸時代に京都からこの地へやって来たのである。縁はおそらくなにもなく、そういう意味では偶然選ばれた地なのであるが、この地方の雪の多さには正直まいったに違いない。途方に暮れたかもしれない。あるいはこれもなにかの縁と受けとめたかもしれない。
横手は雪が多い。牡丹雪が朝から晩まで降りつづくような日が幾日も続くと、このままなにもかも埋もれてしまうのではないかとふと不安になりもする。灰色の空から、雪は倦むことなく、音もなく落ちてくる。その静けさに当てられてしまったように、ものみなひっそりと、息を殺してうずもれてゆくに任せている。わたしは外に立って、額や手のひらに飽きずに雪片を受けつづけたのを思いだす。そして子ども心に無限や永遠といったものへのほのかな予感を感じたのを思いだす。
先祖は真言密教の僧であった。名を宥永といった。元和六年(一六二〇年)、京都で大火があり、それをきっかけに薬師如来の仏像ひとつを背負って都を出、旅の末に秋田にたどりついた。四百年も前のことをこんなに詳しく知っているのは、菅江真澄の書に書いてあるからだが、わたしはこのご先祖にとりわけ深い親しみを感じるのである。
京都を飛びだしたとき、彼はまだ二十代前半の若者であった。この若い男はなにを思い、どんな衝動に、あるいは呼び声に導かれて一歩を踏みだしたのか。大火があったからといって、すべての僧侶が都を捨てて旅に出るわけではない。彼はなにかに不満をもっていたのだろうか。飽き飽きしていたのだろうか。元来ひとところにとどまれぬ者だったのか。あるいは炎につつまれた町を見つめながら、無常の感にとらわれてしまったのか。人に使命を告げるあの内的な声が、彼を動かしたのだろうか。
仏像を背負い体ひとつで飛びだした男の前に、世界は恐いほどに広く思われたはずである。彼はなぜ北へ向かったのか、わたしは想像する。いやしくも宗教家である以上、その人生はおのれに課せられた大なる修行であり、より厳しく、労苦の多い道を目指すことを喜びとしなければならない。僧宥永は若い修行者にありがちな、苦行への熱烈な感情にとらわれていた。厳しくおのれを鍛えるほどに、苦境に身を置くほどに、悟りと救いは近づくのだと考えていた。ありあまる熱情でもって彼は、およそ考えうるかぎり最大の苦行をおのれに課そうとしたのだろう。
彼は北へ足を向けた。数多の関所を越え、多くの山を、川を、集落を越えて、彼は北を目指した。そしてとうとう途方もない雪に遭遇した。彼はおののいた。飽くことを知らずに降りつづく雪に不気味さを感じ、人間の頼りなさと小ささを、同時にまたそのなかで生きぬく人間のしぶとさと生命の強さを感じた。やがて、あらゆるものの上に降りそそぎ、覆い隠すかのような雪のなかに、彼は慈悲に似たものをも見出すようになり、孤独に仏を観想するにふさわしい環境をついに見つけたと思ったのかもしれない。
彼は荒れ果てた小屋を借り、旅のあいだ彼を守り、彼の心を支えてきた薬師如来を静かに置いた。おそれるな、と如来は彼に語りかけるようだった。わたしはいままでおまえを守り導いてきた。これからもそうするであろう……彼は安らぎと決意を得た。そして冷えきった床にひとり座した。
静かに、無心に、降りつづく雪のなかで、彼はおのれのうちへと向かった。すきま風だらけの極寒の小屋に震えながら座り、彼はすべての無明の根源であるおのれの無明のなかへ向かった。寒さは絶えず彼をおびやかし、彼の思考を肉体の感覚へと連れもどそうとする。その震えるおのれの肉体を彼は超越しようとする。長旅によってもう十分に酷使し、痛めつけてきたその肉体とともに、彼はおのれの我欲をも痛めつける。かつて仏陀がそうしたように、それを追いはらい、克服しようとつとめる。
この世のむなしさと苦しみにとらわれ、苦行に苦行を重ねた時期の仏陀と同じ年ごろにいま彼は達している。彼は仏陀に自分を重ねている。仏陀の苦しみを思い自分の苦しみを捧げている。雪は静かに降り、またあるときはびゅうびゅうと音をたてて吹きこんでくる。小屋の隅には吹きつけた雪がいつの間にか白くたまってゆく。しかし彼は目を開かない。彼がいま戦いをいどんでいるものは、その吹雪を超え、寒さを超えている。春はまだ遠い。薄明の差しこむ夜明けまでにも、まだずいぶん遠い。
春のおとずれは遅かった。ある日彼は外がいままでよりもほのかに明るいのを、そして空気のなかに、かすかな気のゆるみにも似た温かみのあるのを感じた。彼は外へ出た。日がやわらかに差していた。梅の木の枝にはずっしりと雪がつもっていたが、いまや少しずつ溶けだして、しずくがしたたっていた。それは陽光を受けて黄金に輝いて見えた。雪に圧迫されながら、梅は人知れず、この冬のあいだにも小さな芽をいくつもはぐくんでいた。彼はふとそのいじらしいさまに涙し、おのれを痛めつけることの愚を、もはやそのような時が過ぎさったのを感じた。
彼は妻帯した。ここからいかに無数のものが生まれたかを思うならば、それはめまいのするような出来事であった。彼の妻帯の末端にいまわたしは属する。彼の悟ったものの先に、わたしはある。労苦をともなった長旅、背中に背負った薬師仏の重さを日々噛みしめ、足を鉛のように感じ、ときに病を得、ひもじさに苦しみもした、その旅のなかで、彼は少しずつこのひとつの悟りと妻帯に向けて導かれていたのにちがいない。
おそれるな、わたしはいままでおまえを守り導いてきた。これからもそうするであろう。
その声の確かさに身を委ねつつ、彼はふと考えた。おれは生命に執着しているのだろうか。そうかもしれない。おれは煩悩にまみれているのだろうか。そうかもしれない。自分の子はかわいく、自分の妻は愛おしい。しかしおれはいまはじめて煩悩のなんたるかを真に理解しているような気がする。この世を真実に生きずして、人はなにを悟ることができようか。なにを人に説くことができようか。おれは家を建て、子を育てる。人々のなかへ入ってゆく。おれはいま真に仏の道を歩もうとしているのだ。
以来わたしの一族は同じ土地に住みつづけている。維新があり、明治になり、檀家のない我が家は僧としての身分を剥奪され、神道に転じた。その末端に属するわたしはもはや仏教や神道の熱心な信者ではない。だが四百年前に、祖先が地上の生の意味を悟ったその地に住み、養われたことをわたしは誇るものである。この事実のみが、あらゆる日々の苦しみのなかでそれでもわたしを生へと導いてきたものである。
生を選ぶための基盤はあやうい。それは決して強烈な根拠を持ってはいない。だから人はなにか自分を生へとつなぎとめるものを持たねばならない。自分の存在を容認することのできる根拠を持たねばならない。実に小さな誇りでいい。他人から見ればまったくくだらぬものでいい。偉人のみが生きるに値するならば、無名の者はどうしてのうのうと生きながらえることができるだろう。わたしはまったく無名の者であり、わたしの愛する先祖も同じく生涯無名の者であった。彼は名を挙げる道を選ばなかった。元来政治的な人間ではなかった。彼は宗教家だった。だが宗教家であるゆえにこそ、この世の無常を超えて家を構え、居場所をもったのである。わたしはその意義の大きさを考える。そしてすべての人にとっての、家を持ち、故郷を持つことの大きさを考える。
ある人は生涯生まれた土地を離れず、ある人はさまざまな事情からそこを離れる。わたしもまた故郷から離れている。だがたとえいま、さまざまな事情のために離れていたにしても、わたしはいずれなにかを悟り、その地へ帰る。もしかすると、生涯その日は来ないかもしれない。なにかを悟るどころか、いたずらにむなしくこの世を送るだけで終わるかもしれない。だがそれでも、その生涯はひとつの大なる修行であり旅であるだろう。わたしはきっと旅の果てに見出すであろう、必要なものはすべて故郷の地において与えられていたのであり、長いことかけてわたしはふたたびそれを見出したのだ、と。
そのときわたしはわたしの生命を誇るであろう。大地の上に立つ足裏を誇るであろう。その足で歩いたことを誇るであろう。費やした労苦を誇るであろう。そのために生じたすべての煩悩と苦しみとを誇るであろう。
故郷よ、おまえは選ばれた地である。ひとりの人間がそこを選び、そこで生きると決めたとき、そのときおまえは選ばれたのである。われわれは皆その無数の選びの裔である。ひとりの人間が居を構える、そしてそこで産み増えてゆく、そのいとなみの偉大さを思え。確かに大地の前に、山々の前に、降りしきる雪の前にわれらはあまりに小さな者である。だがその小さな者がないなら、いったい自然はおのれの美と豊かさとを自覚するであろうか。われらのほかに、誰が万感の思いをもって故郷の風土を讃えるであろう。大地の温かさを歌い、豊穣さを歌い、星々のめぐりに目を凝らし、山をすべての生命の行きつく先と見、いつかそこへ帰ることを夢みる。黄金の田圃で、祝いの歌が響く。労苦の実りを受ける者の笑いが空へ、山々へも響きわたる。いまや山の神は仕事を終えて山へ帰る。神の満足げな眠りのうちに、すべてのものが眠る冬が静かにすぎてゆく。
すべての歌、すべての詩は、ことごとく故郷の風土のなかから生まれる。風土こそが歌でありその生命である。故郷の風土は誰の魂の根源にも静かに根を下ろしている。そしてその人の苦しみのときにも、喜びのときにも、ともに苦しみともに喜ぶ。
わたしは別に大げさなことを云っているのではない。あなたの生きるその大地がいかに美しいかを、いかに豊かであるかを、どうか思い起こしてほしいのだ。たとえそこが過疎地だろうとおそろしく旧弊だろうと、あるいは騒々しい都市であろうと、ありとあらゆる政治的問題が山積していようとも、あなたの故郷の美しさは少しも損なわれず、苦しみの日々にあなたを慰めるであろう。あなたがそこに生まれたということは、あなたに連なる人がその地を選んだのであり、それは誇るべきことなのだ。その誇りからすべての善行が生まれ、その善行からやがて善政が少しずつ芽生えてくるであろう。わたしはそのことを夢みる。故郷の輝く日をわたしは夢みる。それは真実に故郷の風土を愛する者のなかから生まれてくるであろう。わたしは決して絶望しない。故郷の風景がまだ美しくそこにあるかぎり、何人も絶望するにはおよばない。
初出:2020/07/31 雪下第二号