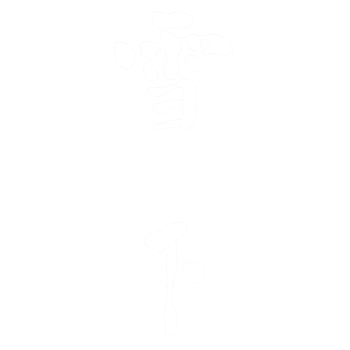これを書きはじめた今日は七月二十四日だが、国立能楽堂へ「鉄輪」を見に行ってきた。安倍晴明生誕一一〇〇年記念だそうである。会場は満員で、若い女性の姿もけっこう見かけた。安倍晴明は、ひとりのキャラクターとして現代文化のなかに完全に定着したのだろう。公演がはじまる前、民俗学者の小松和彦先生が晴明についての小講義をされたが、先生が晴明に興味をもった半世紀ほど前には、安倍晴明といっても誰も知らなかったのに、漫画「陰陽師」の突然のヒットによって一躍有名になってしまった、と少々笑いをこめて話しておられた。
仕舞をはじめてしまったから、わたしのなかで能の見どころが変わってしまった。これまでのように劇のなかに展開する感情だけを追っかけているわけにいかなくなり、わたしの目はシテ(主人公)の足さばきに釘づけになり、所作に釘づけになってしまった。
「舞う」ことと「踊る」こととは違う。「舞う」はそもそもは地面を徘徊することを意味し、「踊る」は跳んだり跳ねたりの上下運動を指す。現在では優雅にひらひらしているのを舞っているという言葉でとらえることが多いが、能の舞の要は、どうも語源からいっても徘徊すなわち足さばきにあるようだ。足さばきという土台の上に、腕の動きが加わり、扇が加わって、舞になる。わたしはいまそのような理解をしているので、足にばかり目がいってしまうわけである。
結局、人はなんのために舞うのだろう。公演が終わったあとで、そんなことを考えた。わたしが舞いはじめた動機は、単純な好奇心である。能に近づくことが、日本的身体技法というものに接近する一番いい方法のように思われたのである。でも、能を見るときいつも、わたしはそういうものとはまったく次元の異なる、ある不思議な感動をおぼえる。それは確かに能楽師の所作の美しさが生みだすものであるだろうし、あの能の舞台という場に漂っているある種の神秘的な気配のためでもあるだろうし、能という劇そのもののもつ宗教性にわたしが感応するということもある。でも、その感動はそうしたもの以上に、能の場において展開される、霊というものに対する繊細で美しい心づかいに由来するように思われる。
わたしが能のシテ(主人公)よりはむしろ脇役の僧に共感するという話は、「鉄輪」のことを書いたときにブログに書いたように思う。それは諸国を放浪し、行く先々で霊をなだめ、なぐさめる人である。能のシテたちは、僧の法華読誦によって成仏する、あるいは地獄に落ちていたのが救われる、などの結末を迎えることも多いが、その結末へ向かう前に、散々に自分の物語を物語り、思いを吐露し、その思いをこめて舞う。旅の僧はそれらを目の当たりにし、すべて心におさめ、それから弔いにかかる。そこには、死者の霊に対するこれ以上ない礼儀や心づくしというようなものがあるように思われる。人の霊というものに対する、かぎりない敬意のまなざしがあるように思われる。人の本質は霊でありその霊は神なのだ。肉体を脱ぎ捨てた霊は、霊としての姿をとり戻し、神に返る。だが神に返る前に、それは地上の人間によって存分にねぎらわれ、なだめられて、敬意をもって送り出してもらわねばならない。
わたしの好きな、アイヌ民族に伝わるとても美しい歌がある。狩ったシカを美しく飾って、あの世に送り返してやる歌である。人間の手で美しく飾られ、心を尽くしてあの世へ送られるシカはとてもよろこび、それを非常な名誉に感じる。だからシカは人に狩られるのであり、人はみずから狩ったシカに対して、心を尽くさなければならない。シカは死に、美しく装いも新たにあの世へ渡り、そしてわたしたちを見守る神になる。
舞や踊りや音楽、饗宴といったものは、本来みな神、あるいは霊に捧げられるものである。かつて、人間の行為はみなそのようなものであった。神と人とはひとつであり、同じ食卓を囲み、同じ舞を舞い、同じ音楽を楽しんだ。かつて、音楽のあるところには神があり、人が舞うところには神があった。わたしたちはともに笑い、ともに涙し、ともに喜びをわかちあった。霊的に孤立した人間は舞を舞わない。舞い得ないのだ。舞う動機が欠けているからである。自分以外のいかなるものへも宛てない舞はむなしいものである。その舞はなにものも呼び起こし呼び覚ますことがないだろう。美は神の霊をまとうとき本物になる。型は歴史をまとうとき本物になる。そうしてすべてをまとった舞だけが、ほんとうに舞と呼べる舞になる。わたしの身体が喜び舞うならば、それはすべてが喜び舞っているのであり、神が喜び舞っているのである。
親戚に、山菜採りを趣味にしている人がある。その人は、山に入る前に、ズボンを脱いで下半身を露出することがあるそうだ。山の神は女なので(これは地域によって違うらしく、男とされている場合もある)、山の神を喜ばせて、首尾よく事を運ぼうというわけである。うまく舞茸など見つかると、舞茸だけにその人は舞うそうである。その喜びは、確かにその人自身の喜びなのだが、その人の喜びの舞は、同時に山の神に捧げるものにもなるのだ。その人が山の神の存在を想っているからである。そして人の心がその存在を想うとき、その存在もまたその人を想っている。
舞の友である扇は、蛇であり祖先神であり神である。扇を扱うことは、それらに礼を尽くすことである。扇は彼らの息吹であり、神の息吹であり、わたしはこの世にいながら彼らを身に帯び、彼らとともに戯れる。あるいは、彼らの霊を慰撫するために舞う。そして扇をひるがえし、足で直線を描き円を描きつつ、いつの間にか、それらとひとつになっている。
そんなことを考えつつ、わたしは舞いの練習をする。わたしの舞はまだ非常にぎこちない。それはまだ霊に届くにはとても足りない。わたしの扇はまだちっとも人のいうことを聞かない。扇の形を手が覚えておらず、わたしの手の形を扇が覚えていないのである。扇のような道具とですら、わたしたちは関係を築きひとつになることができる。時間の積み重ねの中で、わたしたちは双方向に交感し、拡張していき、融合するのだ。そのときわたしの手は扇であり、扇はわたしの手であって、わたしはわたしという身体のうちに、わたしの手のうちに、祖先のすべての霊を抱えこみ、あらゆる霊を抱えこみ、抱きしめるのである。この世にいながら、わたしは彼らをまとうのだ。聖パウロは「キリストを着る」という表現をし、『井筒』のシテ紀有常の女は、在原業平の形見の直衣を身につけて舞う。「今は亡き世に業平の、形見の直衣身に触れて、恥ずかしや、昔男に移り舞い、雪を廻らす、花の袖」
わたしたちが抱いているのは、愛する者と一体化するという、すべてとひとつになるという、見果てぬ夢である。わたしという存在はそのとき別の存在を包みこみ、あるいは別の存在に包まれて、曖昧に溶け去る。わたしはもはやわたしではないが、同時にその中心において強固にわたしでもある。舞はそのような状態をつかの間引き寄せようとして、足裏で地べたを徘徊する宿命にある人間が編み出したもののように思われてならない。それは確かに超越へ向かおうとする運動である。踊りという跳躍の運動は、直接に上をめがける動きであり、これもまた超越へ向かおうとする働きであるが、足が要となる舞は、なにかこの身のまま別の世界へ踏み入っていこうとする、ひどく無邪気で勇敢で無鉄砲な試みのように思われてならない。
能の基本姿勢である構えは、重心が斜め前にかかり、足腰をひどく意識するので、そこに乗っかっている自分の重さを痛感させられる。上半身を前傾させて重心をはずし、そこから腰を引き上げて自分の重さを自分のなかへ引き戻し、膝をゆるめ腰を落としてその重さを具合よく自分のなかへおさめることのできる点をさがす。それは自分の身体の重さを潔く引き受け、それを軽やかな戯れに変える行為のようにも見える。足裏におのれの重さを引き受けて、どこまでもこの身体でこの足で、どこへでも舞っていってみせようというような。
扇を松明のようにかざし、自己の身体の重みを感じながら、このひとりの舞い手は、すべての霊を目指して、同時に自分の後ろにすべての霊を従えているような気がしてならない。
初出:2021/08/01「雪下」第十四号