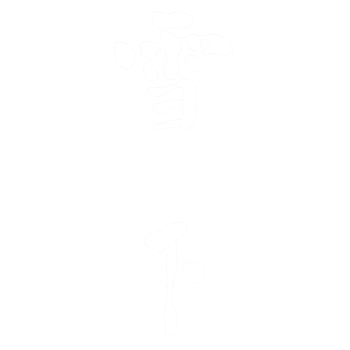9日に、国立能楽堂へ能「蟬丸」を見に行ってきた。公演に先立って、東大名誉教授である松岡心平先生の解説があった。松岡先生の著作をわたしは愛読していて、『宴の身体』や『中世芸能講義』など深い感銘を受けながら読んだけれども、先生は天皇制と日本芸能というテーマについてたびたび言及しておられ、能「蟬丸」は、醍醐天皇の第四皇子である盲目の蟬丸が、帝の命令によって都から追放され逢坂山にやってくるところからはじまるという筋立てであって、いろいろと興味深い話が聞けた。
たとえば、この曲は江戸後期あたりから上演されるようになり、それまではおもに謡の曲として用いられていたこと、昭和十年代ごろから、天皇への不敬罪に配慮してこの曲が禁曲になったこと、それも、そうしろと命令されたのではなくて、能楽協会が自主的に上演を自粛したこと、などである。
最近権威の問題について考えていたのだが、権威と権力の最大の違いは、権威のほうは、権威自身がなにもしないでも、相手に自主的に権威の望むとおりに行動させることができるのに対し、権力は、暴力でもってなにかしらの行為を強制することができる特権を有している点にある。そうすると、天皇とは典型的な権威であって、軍国主義などとはやはりちょっと存在のベクトルが違う。松岡先生は「稚児と天皇制」という非常に興味深い論文を書いているが(『宴の身体』収録)、そのなかで院政期から後醍醐天皇あたりまでの幼児天皇と、天皇制の中空構造について触れている。
中空構造というのは、これは河合隼雄が提唱したものだが、「権威あるもの、権力をもつものによる統合のモデルではなく、力もはたらきももたない中心が相対立する力を適当に均衡せしめているモデル」(『古事記』神話における中空構造『河合隼雄著作集8』等に収録)のことであって、日本の統治とはひとつの絶対的権力があってそれが国家を統合しているのではなくて、空洞の中央のまわりにさまざまな力が分散されてバランスをとっているモデルだということだ。
このへんのことは、平家物語などを読むに当たって院政期のことをちゃんと理解しなければなるまいと思って勉強しはじめたときに学んだ。日本中世を理解するには荘園制度をちゃんと理解しないといけなくて、荘園制度をちゃんと理解するには中世の権力構造というものがどうなっていたのかを理解しないといけなくて、これがまたわかりにくくてわたしはまだよくわからないのであるが、勉強していて思ったのは、日本という国はいまも昔もずっと、この「明確な主体の欠如」というものを貫き通しているなということだった。
たとえば、日本が戦争に突き進んでいったのは軍部が強かったからでも神聖天皇の権威でもなくて、明治憲法下における明確な責任主体や決定機関の欠如ということに非常に大きな要因があったとみることができる。最終的に判断を下すのはだれで、責任をとるのは誰か、ということが、日本ではいつも、常に、曖昧である。政治体としてもそうだし、個人というものもさまざまな側面の統合体であるとみなせば、おそらくその傾向は強いのではあるまいか。
わたしはいまだに、責任というものがなんだかよくわからない。わたし自身というものも奇妙に空洞である。わたしの自己認識は、最近気がついたのだが、透明な自分という入れ物があって、そこにいろんなものがぶちこまれているのだということである。これを書いている人はその透明な箱の中のひとつであって、それを統合しているのは、生まれてきたときに両親によってなにがしという名前をつけられた透明な箱なのだ。自我はそれ以外のものをひとつにまとめておく透明な箱である。
天皇という存在もまた、やはり奇妙に純粋で透明である。それは命令者ではない。絶対者でもない。ただ中央に鎮座している、透きとおった水晶玉のような透明な球体、それが日本の中央であって、その神秘的な水晶玉のまわりをめぐって、巫女は踊り戦士は剣の舞を舞い、人々は円舞しているのかもしれない。その渦巻くエネルギーは、みんな中央の水晶玉に吸収され浄化されて、いずれにせよそれ自身いつの間にか透明になって消えてしまうのである。
ここには、かさついたいかめしい絶対統治者というようなものはない。中央にあるのは、あくまで美しく透明な水晶玉でなければならない。人々は水晶玉を仰ぎ、水晶玉を見つめ、水晶玉が自分たちの汚れを引き受けていることを知っていて、水晶玉の美しさを愛している。猥雑な生命のエネルギーは、水晶玉のまわりをめぐる。そして水晶はそのエネルギーを自身の透明な玉の肌に映しながら、ただ美しく光っている。こういう世界に、唯一神はやっぱりどぎつすぎるように思う。このどぎつい絶対者からの独立が西洋の歴史を作ってきたとすれば、日本は水晶玉のまわりでいつまでも円舞していてもよい。その永久に続く円運動の夢は破られる必要がない。水晶玉はなにも云わないし、なにももたない。水晶玉のまわりで踊るものどもも、なにも云わないし、なにももたない。そこにはただ永遠の輪舞が描き出すエネルギーの流出と浄化があるばかりである。
すっかり話がずれてしまったがわたしはこんなことを書きたいのではなかった。松岡先生の解説を聞いていて、ひとつ宿題をもらったような気がした話をしたかったのだ。
「蟬丸」は、醍醐天皇の第四皇子である盲目の蟬丸が、天皇の命によって逢坂山に捨てられるところからはじまる。その山奥で、姉であり第三皇子である逆髪と偶然再会し、憂き世のつらさをともに嘆いたあと、ふたりはふたたび別れ別れになっていくというのがおおまかな話の流れだが、松岡先生は解説の中で、この最後に別れ別れになるというのが不思議である、ともに暮らしていくという選択肢もあったろうけれども、というようなことを話されていた。それを聞いていて、わたしはなるほど学者というのはこういうことを不思議に思うのか、と思ったのである。
というのも、わたしは前日に「蟬丸」を読んでから公演を見に出かけたわけで、話の流れは知っていた。きょうだいが別れ別れになるということについては、これほど当然な結末はないように思ったので、疑問にも思わなかった。なぜ疑問に思わなかったのだろうと思っていたら、すぐさま答えは出てきて、それは戯曲の形でわたしに訴えてきたので、わたしはこれを書かねばならないと思った。なんだか宿題をもらった気分だというのは、そういう意味である。
姉と弟ということを考えるとき、わたしはすぐに旧約聖書のアブサロムとその姉タマルの話を思い出す。アブサロムもタマルもダビデ王の子である。美しく聡明なタマルは、ある日異母兄のアムノンに犯され、辱めを受ける。だがアムノンは長子だったことから、ダビデ王はこれをとがめなかった。タマルは同じ母親をもつ弟アブサロムのもとで、わびしく暮らすことになる。
二年後、アブサロムは兄たちを招いて宴会を催し、自分の従者たちに、酔っ払ったアムノンを殺させるのである。これがきっかけでアブサロムは逃亡し、のちにダビデに対し反乱を起こすことになる。アブサロムは、自分の娘にタマルという名をつけている。姉を愛していたのである。
結局、アブサロムの謀反は成功せず、最後は槍で突かれて命を落とすのだが、それを知ったダビデの悲痛な叫びに胸の痛まない者があるだろうか。
「わが子アブサロムよ、わが子よ、わが子アブサロムよ。わたしがおまえの代わりに死ねばよかったのに。アブサロムよ、わが子、わが子よ」
ここに王という立場の人間の悲劇があり、父であるより先に統治者でなければならぬ者の苦悩がある。盲目の息子を山に捨てよと命じた醍醐天皇も、これと同じ種類の苦悩を味わったのではなかったか。盲目の蟬丸は、あきらかに欠陥やほころび、凶事などの象徴である。それを山に捨てることによって、そうしたものを葬り去る、あるいはあの世に返すのかもしれないが、そのことによって天皇は純粋さを保つことができるわけである。日本が純粋であるには、天皇が純粋であればよい。そうして罪科を引き受けた蟬丸は、ひとり山奥で仏道に専心するわけである。
ちなみに姉の逆髪は、髪が逆さに生えてくる一種の奇形で、あちこちをさまよい歩く狂った女である。これもまた宮中から、都からは追放された存在である。そのふたつのものが、山の奥深くで出会う。彼らの別れは必然である。文学者には、こういうことが手にとるようにわかる。