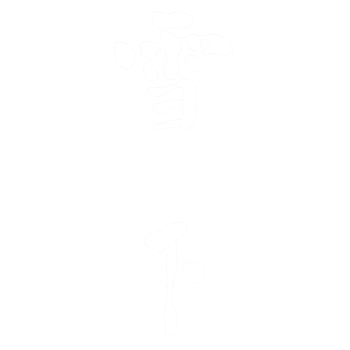こないだ雑誌にカリグラフィーをはじめた旨を書いたけれども、わたしには十二世紀の北ドイツで写字生をしていた過去がある。なぜ十二世紀なのかは知らない。十字軍の世紀とか、もっぱら修道士が写本の文字を書いていた最後の世紀だからとか、考えられる理由はいろいろあるけれども、そんなことはどうでもいい。とにかくわたしが昔修道士をしていたことについては疑いようがない。多くの人と同じように、わたしにもさまざまな過去があり、十二世紀ドイツの修道女にして写字生ウルスラはそのうちのひとりであるにすぎない。名前まで判明しているのはめずらしいが、知っているのだからしようがない。なぜ知っているのかはぜんぜん知らないが。
すべての人間と同じように、このウルスラにも彼女の人生というものがあった。わたしは先だって、ペンをもって文字を書いているとき、このウルスラの過去を見た。それは次のようなものだった。
よく日の当たる写字室で机に向かっていた尼僧ウルスラは、写字室に入ってきた別の修道女に呼ばれた。なんでも近くの村の百姓のおかみさんが、いよいよ具合が悪いという。ウルスラは手がけていた一文を最後まで仕上げ、ピリオドを打った……「その若い娘は姿がとても美しく処女で、男を知らなかった。」……ウルスラはリベカの描写にかかっていたのである。のちにイサクの妻になる若いリベカ、水瓶をもって水場へ水を汲みにやってきたリベカ、みずみずしく美しいリベカ。ウルスラはもう嫉妬をおぼえなかった。そうしたものはすでに過ぎ去り、彼女はいまでは中年の、経験を積んだ修道女だ。ウルスラもかつては美しかったことがある。だが彼女はそれを神に捧げることを望んだ。もともと神が創ったものであったから。
疲れをふり落とすように軽く首をふって、どこまで書き写したか忘れないように紐の切れ端で結び目をつくり、ウルスラは立ち上がった。そして役に立つ薬草や湿布のつまった仕事道具一式をもって百姓の家へ向かった。
おかみさんは確かにいけなかった。ウルスラはそれが労働と多産と栄養失調の混合物が引き起こした病であることを知っていたが、それは云っても仕方のないことだった。夫を元気づけ、部屋の隅で泣いたりけんかしたりしている一ダースもの子どもたちを叱り飛ばしたり外へ出したりして、薬を処方し、立ち去ろうとした。百姓は申し訳なさそうな顔で、お礼をしたいがあいにく差し上げるものがなにもないと云った。ウルスラは怒ったような顔で、きっぱりとこう云った。
「それ以上云ったら二度と来ませんよ。妻が死にそうなときに、夫が気にかけているのが謝礼のことだなんて、情けないったら! 与えられたものは潔く受けとりなさい。そして感謝を神に返すのです」
ウルスラは確かに、リベカのようないわば極上の絹とでもいうような、どこもかしこも柔らかい処女とは云いがたい。だが彼女は自分が選んだ人生がどういうものかを知っている。自分からなにが失われ、代わりになにを得たのかを知っている。多くの祈りと涙の中で、ウルスラはそれを知ったのである。
これはフランス国立図書館所蔵の写本『Recueil d’anciennes poésies françaises』より、執筆するマリー・ド・フランス。マリー・ド・フランスは十二世紀後半にイングランドで活動していたというフランス生まれの詩人だが、当時の写字生スタイルをよくあらわしているので、われらがウルスラもこのように、片手にペンを、もう片方の手に羊皮紙を押さえるため、ペンを削るため、誤字を削りとるため、等々多くの役割を担っていたナイフをもって書いていたに違いない。
この時代には、写字生が写し間違えた文字を集める悪魔がいて、写字生の死後、最後の審判のときに、その悪魔が集めた文字を「これだけあるぞ」と見せておどかすと信じられていたらしい。というのも、写字生が万が一聖書の一部を写し間違えたり書き落としたりしたら、文言が変わってしまい、大変なことになるからだ。悪魔は信仰を広めないために、聖書や祈祷書を書き写すという重要な役割を担っている写字生に対し、さまざまな妨害をした。眠気を起こさせたり、インクをこぼしたり、書き間違えさせたりうっかり数行飛ばすように仕向けたりと、妨害行為は実に多岐にわたっており、写字生たちは篤い信仰を武器とし鎧として、これら悪魔の奸計に単身立ち向かわねばならなかった。
われらがウルスラも、日々神に祈りながら作業をおこなった。それは命がけの労働であり祈りであった。実際、労働と祈りはほとんど同じことを意味する。文字を書くことと祈りとは、ほとんど同じ行為である。
今日わたしのウルスラを皆さんにご紹介したので、彼女がその名前をもらった聖ウルスラについてもご紹介しておこう。ウルスラはドイツケルンの守護聖人で、中世には非常に崇拝されていた。ウルスラはブリタニアの王女で、異国の異教徒の夫に嫁ぐため、一万一千人の乙女とともに船出し、フン族に包囲されていたケルンの地で、それらの乙女たちとともに殉教したそうである。
この画像はとても小さいので見づらいと思うが、画面の一番で王座に座っているのが聖ウルスラである。そのまわりには、殉教した乙女たちの首が環状に並べられている。枠の外には、右に剣をもった長髪の蛮族の男が、左からは同じく弓をもった男が、聖ウルスラを狙っている。\r\n この絵の上部の円も同じくケルンの聖人で殉教者である聖ゲレオンの物語を描いたものだ。ローマ兵士ゲレオンは、戦の勝利を祈願するため異教の神々に犠牲を捧げるよう命令されたが、信仰からそれを拒んだので、仲間たちとともに首を切られ、首は井戸に投げこまれたという。画家はこの物語を表すために、円の中央に首の浮かぶ井戸を描き、その周りに首のない胴体を配置した。
ほんとうは聖ウルスラを紹介するのに、こんな小さい画像をわざわざ使わなくてもいいのである。でも、どうしてもこれを使用したかったのは、この絵がおそらくわたしと聖ウルスラの最初の出会いであり、またわたしが写本に目覚めるきっかけになった本、E・H・ゴンブリッチ『美術の歩み』(友部直訳、美術出版社、1972年)に掲載されていたからだ。
わたしが絵の見方を教わった決定的な本は三冊ある。このゴンブリッチの著作と、ロベルト・ロンギ の『イタリア絵画史』、それに坂崎乙郎先生の『夜の画家たち』だ。どの本も全部すばらしい。でも、ダントツで最初の一冊におすすめできるのはゴンブリッチの本だ。美術の歴史を通史として学べるし、それぞれの描写に向けるゴンブリッチの目は素晴らしい。
わたしがなにを教わったかというと、つまりこういうことである。六世紀から十一世紀までのヨーロッパ美術を紹介するのに、彼はいくつかの写本や建築物とともにバイユー・タペストリーを選んでいる。七十メートルもあるタペストリーというか正確には刺繍が施された布で、1066年のウィリアム征服王によるノルマン・コンクエストを描いた作品だ。こういうやつである。

絵の右側に、バルコニーにいて、手をかざして海の彼方を見つめている男が描かれている。ゴンブリッチは、この男の描写についてこんなことを書いているのだ。
バルコニーの上にいる男が、私は特に好きである。……彼の腕や手指は、どちらかといえば奇妙に見えるし、……変に小っぽけなマネキン人形のように見えることも確かである。この時期の中世の芸術家たちは、模倣する手本をもっていない場合、子供のように描いた。それをおかしいと笑うのは簡単だが、彼の描いたように描くのは決して容易ではない。彼はこの叙事詩を、このように簡潔な手段と、重要に見えるものへのひたむきな集中で描いたが、それは、現代の従軍記者やニュース映画作者の報道よりも、ずっと印象的なものとなっているように思われる。
われらが聖ウルスラの紹介は、その次の章、十二世紀のヨーロッパ美術を紹介する章に出てくる。そこでは彼は、画家が見えるものを見えるとおりに表そうとする野心を捨て去ったとき、どんなすばらしい絵が生まれるかについて書いている。
これもまた同書で紹介されている、1150年ごろにスワビア(シュヴァーベン)で作成された写本の挿絵である。

ゴンブリッチが、この画家は現実的な絵を描こうとしたのではなくて、受胎告知の神秘を描こうとしたのだと説明してくれたので、わたしはこの一見あまり「上手」には見えない絵がどんなにすばらしいかを理解した。ガブリエルから告知を受けるマリアの手の描写を見てほしい。絵を見るときに、手を見ないのはバカのすることだ。手というのは、画家にとってはそれだけをひたすら練習するに値する、尽きることない表現の泉みたいなものらしい。親指が合わさるほど近づいたマリアのこの手、このサインがどれほどのものを暗示し、また象徴しているように見えるか、ちょっと信じられないほどである。この構図はひとつの型であって、同じような絵はほかにいくつもあるのだが、マリアの手の描き方はけっこうばらばらである。この絵を描いた画家は、このマリアのしぐさの意味やそれが象徴しているものを、ちゃんと知っていて描いたように見える。そこにひそんでいるあらゆる神秘を、この手だけで、画家は描くことに成功しているように見える。
中世写本がどんなに愉快で楽しい絵に満ちているか示すために、最後に聖ベネディクトゥスを描いた一枚をご紹介しよう。これはわたしが模写しようと思って、『ワインと修道院』(デスモンド・スアード、朝倉文市・横山竹己訳、八坂書房、2011年)なる本のなかから写真に撮っておいたものである。これも十二世紀の写本の挿絵である。
この聖ベネディクトゥスは、ベネディクト会を創設したあのベネディクトゥスだが、自ら作った戒律を執筆している。このなんとも明るく温厚なベネディクトゥスの描写も魅力的だが、その左に描かれている、はしごを上り下りする天使の描写がわたしは好きなのである。ぜひクリックして拡大して見てほしい。これはヤコブのはしごと呼ばれる主題だが、兄エサウの恨みを買って逃亡したヤコブが、ある夜、石を枕にして寝ていたら、こんな夢を見た。先端が天に届く階段が地に立てられて、神の使いたちがその階段を上り下りしていた。そして階段の上には主が立っていて、ヤコブに、おまえが横たわっているこの地をおまえに与え、おまえの子孫を大地の塵のように多くする、と告げて祝福するのである。
この絵においても、はしごの上には主がいて、祝福のポーズ、あるいはこれは話しかけを意味するポーズかもしれないが、ともかく右手を挙げている。はしごの下にはヤコブが石を枕に寝ていて、はしごを天使が上り下りしている。この上り下りの描写がわたしは好きなのだ。はしごを上ったり下りたりしているところを描くのは難しい。上りと下りを区別するのが難しいからだ。単にはしごに手足をかけた天使を描いただけでは、上っているのか下りているのかわからず、聖書の描写に忠実ではなくなってしまう。そこで「上り下り」を示すために、天使の向きを変えたのである。上っている天使は頭を上にして進み、下りている天使は頭を下にして進んでいる。これで、「上ったり下りたり」がばっちり描写でき、見る人も天使がなにをしているかひと目でわかるようになった。よかったよかった。
現代人の場合、もう子どもでもこんなふうに描いたりしないかもしれない、とわたしはひそかに危惧したりする。少なくとも、絵を描くということに意志的な子どもにとって、現代はうまく描くための手本にあふれている時代だから、才能さえあれば早々に、子ども時代のピカソくらいのデッサン力をもてるかもしれない。でもわたしは逆さに描かれた天使や、不自然に腕が丸まった男がやっぱり好きである。逆さの天使や驚くマリアや聖ウルスラは、写実的な描写とはまた別の意図をもって、また別の目的のために、ほんとうにぜんぜん別の目的のために描かれている。これらはみんな、お話を正確に伝えるため、あるいはそこに働く神の力を示すために描かれているので、画家はそのために奮闘しているのであって、オリジナリティなどのために苦心しているのではないのだ。
わたしはオリジナリティというものをあんまり尊ばない。そういうのはなにか見苦しい、三流の努力というような感じがとてもする。誰にでも読めて、誰にでも書けるようなもの……でもそういうものを書くのがほんとうは一番難しいということ、誰にでもわかるようにするためにはどれほど途方もない苦心が必要かということを、これらの写本は教えてくれるような気がする。写本に描かれた物語を読み解くのはほんとうに愉快な作業だし、型や手本に則って絵を描きながらも画家の力量や個性は明らかである。そう思うわたしはやっぱり中世人なのであろう。作品を作る自分などというものはどうでもよくて、自分の技術でもって自分より大きなもののために奉仕できるということが、自分にしか作れない作品を作るなどという動機より、やっぱりはるかに偉大なことだとわたしには思えるのだ。